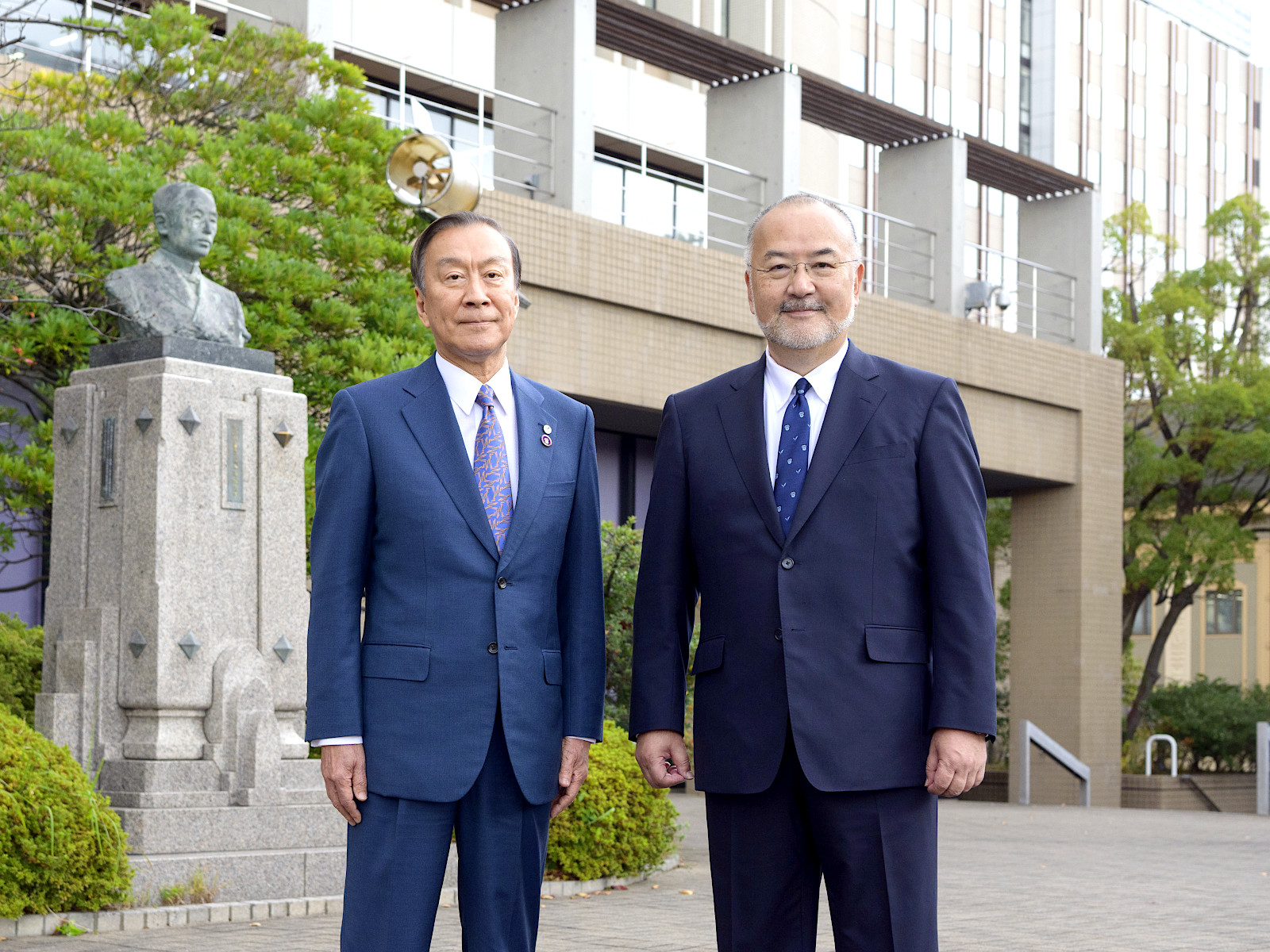新春対談として「明治大学の未来を語る」と題し、柳谷孝理事長、上野正雄学長に年頭所感も含めてお話を伺った。
 左から柳谷理事長、上野学長
左から柳谷理事長、上野学長2025年をさらなる飛躍の年に

柳谷孝 理事長(以下:柳谷) 新年あけましておめでとうございます。昨年来の世界情勢に目を向けますと、ウクライナや中東での戦火は、世界の分断を一層加速させるとともに、資源価格や為替市場などの経済にも大きな影響を与え、国際社会には不透明感と緊張感が増しています。
また、ChatGPTに代表される生成AIは新たな産業革命と呼ばれ、さまざまな分野で革新的な活用が期待されています。その一方、世界経済フォーラムが昨年のダボス会議前に公表したグローバルリスク報告書では、「誤報と偽情報」がこれからの最も大きなリスクとされ、AIが選挙介入からサイバー犯罪や軍事目的に至るまで、あらゆる場面で悪用される危険性を指摘しています。
私たちはこうした先行き不透明な時代だからこそ、羅針盤となる未来を探っていかなければなりません。そのために、明治大学はこれからも人類と地球環境の調和した未来を創造することに貢献できる有益な人材を広く社会に送り出すべく、教学と法人が一体となってその実現に取り組んでまいります。
さて、本年の干支は「乙巳(きのとみ)」です。困難があっても紆余曲折しながら進むことを意味する「乙」と、脱皮を繰り返すことから変化や成長、再生を象徴する「巳」。この組み合わせから「乙巳」は、変化しながら困難を乗り越え、成長や発展を続けていく年であるといわれています。さらに「巳」は金運の象徴とされ、大変縁起のよい動物とされています。
本学もアジアのトップユニバーシティを目指し、2025年をさらなる飛躍の年にしたいと考えています。

上野正雄 学長(以下:上野) あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、来年のことを言うと鬼が笑うそうですが、今年のことなら、大笑いはされないのではないかと思います。という前置きも必要ないほどに、明らかなことがあります。いわゆる「2025年問題」です。
今年、団塊の世代800万人全員が後期高齢者となり、これまでの高齢化の進展の「速さ」から、いよいよ高齢化率の「高さ」が問題となるということです。労働力人口不足の質的変化や社会保障の負担など、多くの局面で日本社会は一層の困難に直面するといわれています。
新年早々、意気消沈するような話ではありますが、大学も一緒になって意気消沈する必要はないと思っています。労働力人口が不足するなら、一人一人のスキルを上げれば良いわけで、そこには教育機関としての大学の大きな活路があります。
これまで、例えば日本企業は、採用にあたって学修成果を重視してこなかったところがあるようですが、これからはそうはいかなくなります。とすれば、人類が抱える課題を明らかにし、解決する方策を示す研究を進め、人材を育てることができる大学にとっては、大きく飛躍できるチャンスになるはずです。そして、10学部16研究科を展開することができる1000人の専任研究者と600人の専任職員を擁する明治大学は、それができる大学です。今日の対談のテーマは「明治大学の未来を語る」ですが、結論を先に述べれば、明治大学の未来は「明るい未来」です。
将来見据え大型プロジェクト始動
――2024年の明治大学を振り返っていただけますでしょうか
柳谷 皆さまご承知のように、NHKの朝ドラ「虎に翼」は高視聴率で大変好評でありましたが、おかげさまで本学に対する注目度や評価も大いに高まりました。実際リクルート進学総研が2024年に公表した関東甲信越エリアの高校生が進学したい大学のNo.1は明治大学でありました。
さて、この「虎に翼」と同時期にスタートした今理事会ですが、本学の抱える大きな課題の解決や将来への布石となる大型プロジェクトが着実に動き出した年となりました。
まず1点目として、2025年4月から「大学年金新制度」の導入が決定したことが挙げられます。これまでの教職員向けの大学年金は、不足責任準備金の多さから将来の安定した制度維持が危ぶまれており、これが永年の経営課題となっておりました。また同時に、定年までの在職年数が17年未満で、大学年金の加入対象とならない教職員への対応も必要とされていました。
こうした背景から、将来債務が発生しない新制度である「確定拠出型年金制度」(DC制度)を、新規入職者と現在の明大年金未加入者から導入することについて、教職員組合と約3年間にわたる団体交渉を重ね、2024年7月に協定書を締結しました。DC制度の導入後も、現在の大学年金に加入されている方は、今まで通りの年金制度が適用され、かつ、年金財政状況が改善されることで、制度の安定維持が図られます。
一方で、DC制度適用者には、今まで年金に加入できなかった教職員が加入できることになったことや、多様な働き方に応じた柔軟な対応が可能なポータビリティがある点など、さまざまなメリットが想定されます。本学としては、教職員が安心して教育・研究に専念・支援できる体制を整えると同時に、将来の財政改善も両立できる制度として、大いに期待しているところです。
次に2点目ですが、本学は2024年11月に、数多くの文豪が利用したことで知られる「山の上ホテル」が建設されている土地、建物を取得しました。現在の外観を維持したまま、必要な改修工事を施した上で、専門業者と連携しホテル機能を継続させるとともに、学生支援、地域連携、社会連携の機能としても利活用できるよう検討しております。
山の上ホテル本館は、本学校友であり本学専門部女子部校舎建設も支援された佐藤慶太郎氏の寄付を基に1937年に建設されました。この歴史的・文化的価値のある建物を、今後は本学の新たなシンボルとして継承していくこととなります。本学では、この事業を創立150周年記念事業の一つに位置付け、今後のさまざまなPR活動にも活用していく予定です。今回の取得が次世代の有効活用を考慮した長期的な視点に立った施策であることを、ご理解いただきますようお願いいたします。
そして3点目は、「駿河台キャンパス総合施設整備計画」についてであります。本計画は、2031年の創立150周年に向けて明治大学のあるべき姿を定めた「MEIJI VISION 150-前へ-」における施設整備計画の重点目標として位置付けられており、駿河台キャンパス猿楽町地区の老朽化した校舎を中心に、キャンパス全体に及ぶ施設の建て替えと改修を14年の期間をかけて行う総合的な施設整備事業となります。
また、本計画は、現在中野キャンパスに配置されている全機関を、約10年後に駿河台キャンパスに統合することを前提とした計画であり、本学のキャンパス編成において大きな転換期を迎えることになる計画です。この中野キャンパスと駿河台キャンパスとの教育・研究の融合によるシナジー効果で、より高度で先進的な教育・研究が駿河台キャンパスで展開できるようキャンパス環境を再整備します。なお、統合した後の中野キャンパスの利用については、今後の大学へのニーズなども考慮して理事会において検討してまいります。
新たなキャンパスでは、新教育棟、新研究棟といった新しい教育・研究施設の建設をはじめ、学生課外活動の場となるスチューデントセンターの建設、その他の既存校舎の改修を施した上での諸機関の配置変更など、大規模な建設移転計画が予定されており、駿河台キャンパスの次世代の発展を見据えた一大改革事業がこれから本格的に始まることとなります。
以上3点について申し上げましたが、昨年は本学が創立150周年はもちろん、その先の未来に向けて輝き続けていく上で、極めて重要なプロジェクトを取りまとめることができた1年となりました。
上野 まず、学長室を中心に振り返りたいと思います。4月に副学長と学長室専門員によって構成される学長スタッフが動き始めましたが、その人数をいずれも半減させました。学長室の議論を実質化することで、スタッフ全員が教学全体の状況を把握し、その上で、各自の担当業務に当たってもらいたいという趣旨です。スタッフの先生方の負担は増えてしまいましたが、談論風発の中で、担当の内外を問わず、それぞれの案件の位置付けを理解していただき、うまく機能しています。
また、4月以降、その学長スタッフで検討してきた「学長方針(基本方針、重点戦略)」が、学長室の研修会などを経て「年度計画書」として完成し、9月末に理事長に提出しました。学長に就任して最初の学長方針ですので、2025年度の方針であると同時に基本的に学長任期中の方針ともなるので、より多くの方に読んでもらえるよう、例年と比べてほぼ3割減として、可能な限りシンプルなものにしました。
基本方針の内容としては、明治大学の多様性を一層広げていきたいということが基礎となっております。教育では、学部・研究科間の垣根を低くして、大規模総合大学であるからこそ可能な広く深い学びを提供することによって、学生に多様な視点を持たせたい。研究では、多様な学問分野を連携するコンバージェンス型研究を可能にする環境を提供したい。学生の学びやキャリア形成、留学、課外活動などの活動を支援し、教員の教育・研究環境におけるウェルビーイングを向上させることで、学生や教員の多様性がより尊重されるようにしたい。例えば、このようなことです。
この他、2024年の学長室での取り組みとしては、「学長室だより」をデータ発行に変更し、一部記事を学外にも公開したこと、「学長フォーラム」として、各キャンパスで専任教員との自由な意見交換の場を設けたことなどが実施に至りました。また、2024年に、学長室を中心とした検討が一定程度進んでおり、そろそろ具体的な制度として提案できる予定のものとして、副専攻制度の創設、海外の大学に中長期の留学をする学生への助成金制度の再構築、起業・スタートアップ支援体制の整備などがあります。
次に「駿河台キャンパス総合施設整備計画」と「山の上ホテル」について、教学の立場から振り返りたいと思います。中野キャンパスは、国際日本学部と総合数理学部という類例のない文理の学部が置かれた、極めて先端的なキャンパスとして設置されたわけですが、その文理を超えた連携と国際化は非常にうまく進んできました。
しかし、20年の時を経て、文理の連携も国際化もいずれも、もはや先端的なものではなく、大学全体に普遍的に及ぼされるべきものとなってきた今、その実績を踏まえた影響を駿河台キャンパスにも拡大することは、駿河台の文系6学部にとっても、また中野の2学部にとっても有用であり、必要なこととなってきたわけです。
そう考えたとき、中野キャンパスの機能と駿河台キャンパスの機能が一体化することによる教育と研究の一層の充実は、教育研究機関である明治大学の百年の計として、ぜひ進めていくべきものと考えています。
山の上ホテルの取得についても、まさに百年の計として捉えていくべきものと考えています。種々さまざまな考えを持った3万5000人の学生、60万人の校友、そして多くの現役・退職教職員が一体感を持って、明治大学を支えていくには、シンボルが必須です。それが、理念的には「権利自由、独立自治」の建学の精神であり、物的には以前は記念館でした。場合によっては、大学スポーツもそのシンボルたり得ると思います。そして、山の上ホテルの建物は、その歴史的な物語からしても、記念館に代わるものとなります。
付言すれば、DX(デジタルトランスフォーメーション)の発達などで広い校地が不要となったときにも、駿河台で最後に残すべきは、あの一角であることは間違いないでしょう。明治大学にとって、まさに「当年の費えといえども後世の頼り」になるものです。
最後に全学的な教育研究に関わるものとして、文科省の2つの補助金事業に採択されたことを、お話させていただきたいと思います。一つがデジタルなど成長分野を牽引する高度情報専門人材の育成に向けた「大学・高専機能強化支援事業」に申請した「数理データサイエンス人工知能エキスパート育成プログラム」で、総合数理学部・大学院先端数理科学研究科の定員を増やすとともに、研究科に2つのコースを設置することになります。
もう一つが研究論文などを内外に広く公開することで学術研究の発展に寄与することに向けた「オープンアクセス加速化事業」に申請した事業で、今後、明治大学の学術成果の世界に向けた公開をより一層推進していくことになります。いずれも、明治大学の教育と研究が評価され、期待された結果です。
 リバティタワー23階岸本辰雄ホールにて。左は聞き手の黒澤睦副学長(社会連携担当・広報担当、学長室専門員長)
リバティタワー23階岸本辰雄ホールにて。左は聞き手の黒澤睦副学長(社会連携担当・広報担当、学長室専門員長)世界に開かれた大学に向け「前へ」
――2031年に迎える創立150周年やその先の明治大学について、長期ビジョン、グランドデザインなどで示されている姿についてお聞かせください
柳谷 2024年11月文科省の諮問機関である中央教育審議会の特別部会は、現在約62万人の大学進学者数が、2050年には42万人へ減るとの試算をまとめました。激減ですね。この答申書では「危機に合わせた対応をしなければ、今後は経営破綻に追い込まれる大学がさらに生じる。再編・統合や縮小・撤退を支援することが必要だ」としています。
一方、国立社会保障・人口問題研究所(IPSS)による最新の人口推計の中で、日本全体の外国人の人口は、2020年の275万人から2070年には939万人と総人口の1割を超えると予想されています。2056年には日本の総人口が1億人を割るからです。中でも18歳から34歳の若い年齢層では、2035年に外国人の人口が1割を超えると予想しています。10年後は若者の10人に1人が外国人という、今より多様性の高い環境となります。
このような環境変化の中で、本学の創立150周年やその先の未来を見据えますと、強い危機感を共有しながら、さらなる発展に向けたグランドデザインを構築していくと同時に、その実現に向けた具体策を中期計画などに盛り込み、定期的に進捗状況を確認しながら各年度の予算編成や事業計画に反映し、実行していく必要があります。既に本学では2021年の創立140周年記念式典において、「MEIJI VISION 150-前へ-」を公表しておりますし、中期計画もスタートしておりますが、こうした「戦略志向の戦術展開」がこれからの時代には求められます。
ちなみに、これまでの30年間を振り返りますと、本学の学生数はほぼ横ばい水準ですが、キャンパスの面積は1.9倍になっています。大学進学者数の減少が本格化する時代が幕開けた中でのキャンパス整備は、スクラップ&ビルドを基本とし、実物空間と仮想空間を融合し、さらに多様な学生たちの集うキャンパス内のグローバル化を実現していく必要があります。これらの考えに基づいて2024年12月に発表したのが、「駿河台キャンパス総合施設整備計画」です。和泉、生田のキャンパスや体育会施設を含め、本年はローリング計画に基づいた具体的な整備をスタートいたします。
明治大学が「世界に開かれた大学」そして「世界に発信する大学」として未来に輝き続けていくために、私も学長と共に先頭に立って邁進してまいります。
上野 理事長、心強いお言葉をありがとうございます。私は、これまでの明治大学がそうだったように、6年後の創立150周年に向けてはもちろん、その先においても、「権利自由、独立自治」に徹底的にこだわっていくべきだと考えています。それは、私学としての明治大学の存在理由がここにあるからです。
創立以来、さまざまな困難の中でも放擲(ほうてき)することなく「権利自由、独立自治」の旗をかざし続けてきた明治大学が希求する社会、すなわち、一人一人が個として尊重される社会は国内外を問わず、いまだ実現をみていません。
とすれば、明治大学は、これからも、その実現に向けて、教育と研究の分野において、社会を牽引していかなければならない。そのために、強い個を育み、お互いを尊重し合える、強くしなやかな人を輩出していきたい。研究者の知を結集して一人一人の個を尊重できる環境を構築したい。
具体的には、大学の全てにわたって多様性を大きく広げていくことによって達成したいと考えています。150周年に向けた「MEIJI VISION 150-前へ-」においても、各所で繰り返し多様性ないしそれにつながる言及がなされていますが、多様性の中からこそ、進化も変革も生まれるとすれば、それは、その先においても極めて重要なグランドデザインの要素になっていくはずです。
国内外から国籍、人種、文化、性別、年齢などにおいて、多様な学生を受け入れて、多分野を連携させた学びの機会を提供する。それと同時に、多様性に配慮したキャンパスを整備し、キャリア形成や課外活動、就職活動などの支援を充実させる。教員・研究者の給源を多様化し、学部・研究科の垣根を超え、大学の枠も国の枠も超えた学際的研究を推進する。地域連携を深めることで、大学の国際化と同時に大学の地域化を進める。
「その先の明治大学」として、このような多様性に満ちたイメージを持っています。例えば、「駿河台キャンパス総合施設整備計画」が10数年かけて現実化する過程においても、このような観点での取り組みがなされていくことを期待しています。その意味では、「駿河台キャンパス総合施設整備計画」は、和泉、生田両キャンパスにとっては、その将来像を明らかにするパイロットプロジェクトと捉えることもできるのではないかと思っています。
そして、冒頭にも申し上げましたが、明治大学は、このような多様性に満ちた明るい未来を実現できる大学であります。
より海外留学しやすい助成制度を
――「明治大学の明るい未来」の達成に向け、2025年に取り組んでいくこと、その意気込みをお聞かせください
柳谷 まず財政についてですが、皆さまご承知のように2023年度決算におきまして、企業の純利益に相当する基本金組入前当年度収支差額は66億9000万円のプラスと、近年にない好決算となりました。「MEIJI VISION 150-前へ-」で掲げた2031年度までに50億円を達成するという重点目標を8年前倒しで実現することができましたが、決してこれに甘んずることなく、本年からは基本金組入前当年度収支差額50億円を安定的に達成できる財務基盤の構築に取り組んでまいります。
次に情報化戦略について申し上げますと、MUX(Meiji University digital Transformation、マックス)の下、本学の抱える膨大な情報の統合管理を進めているところです。6プログラム、17プロジェクト体制で計画を進行中で、これにより教学マネジメントや教育の質保証、学生の学び支援、法人IRの整備・強化による法人の経営戦略立案に利活用し、学生や教職員の創造力や生産性の向上を支えてまいります。
また、付属校政策につきましては、大学進学者数の減少を見据え、あらかじめ優秀な生徒を確保していく必要があるとの考えで、学校法人日本学園と系列校化の協定を締結いたしましたので、2024年5月より理事会メンバー9名中、本学から5名を派遣し、日本学園との緊密な連携体制が整いました。2026年4月1日からの明治大学付属世田谷中学校・高等学校そして男女共学校の誕生を目指し、本年も着実に計画を推進してまいります。
最後になりますが、校友会は明治大学を支える重要なパートナーであり、明治大学総合ニュースサイト「Meiji NOW」や校友に特化したメールマガジン、SNSなどを有効活用し、大学の最新情報を配信していくことによって、大学と校友とが相互に支援し、永続的な発展を目指す関係性を構築してまいります。具体的には、校友会への若手や女性の参加、地域支部の活性化、そして海外紫紺会を含む各紫紺会との連携強化などについて、本年は学校法人といたしましても校友会と一つになって、それらの課題を解決することに尽力してまいります。
また、「元父母の会」も父母会創立50周年を機に2024年よりスタートし、会員も着実に増えておりますので、私も名誉会長として引き続き発展を支えてまいります。
校友会、ご父母、教職員の皆さま、本年も共に力を合わせて「前へ」と進んでまいりましょう。
上野 先ほど申し上げた、副専攻制度の創設、海外の大学に中長期の留学をする学生への助成金制度の再構築、起業・スタートアップ支援体制の整備を他に先行して具体化することを目指しています。
副専攻制度は、学生が多様な視点を持ち、対象を多角的に見ることができるようにしたいという意図に基づく制度です。一つの専攻をしっかり学ぶことはもちろん大事なことですが、それに加えて、もう一つ、専門外の分野についても学ぶことによって、学生の視界は大きく広がるはずです。
具体的には、各学部などがすでに設置開講している科目の中から、基礎的な専門科目を一定数、体系的に選択して提供し、その科目群を修得した他学部の学生に修了証明書を発行するということを考えています。将来的には、明治大学の全学生が副専攻を履修することを必須にし、明治大学の教育の目玉の一つにできればと考えていますが、当面は希望する学生を対象として実施していく予定です。
海外の大学に中長期の留学をする学生に対しては、明治大学はこれまでも海外留学助成金制度と海外トップユニバーシティ助成金制度の2本立てで手厚い助成をしてきましたが、昨今の海外の物価高や円安の影響の中で、留学を希望する学生の状況にはなかなか厳しいものがあります。そこで、これらの助成金の総額を一層拡充していただいた上で、2つの助成金制度の内容を目的合理的に見直して、明治大学でしっかりと学んだ学生に対して、より留学をしやすくなるような助成の制度を整備したいと考えています。
学生の起業・スタートアップ支援については、学生のニーズはもとより社会のニーズも高いものがありますが、これまで明治大学では全学的な取り組みがなされていませんでした。校友や明治大学を応援してくださる方々の協力も得られていますので、明治大学らしい支援体制を構築したいと考えています。
また、明治大学付属世田谷中学校・高等学校が来春からスタートします。2025年はそれに向けた準備を着実に進めて行きます。
大学4年間に加えて、中学、高校の3年ないし6年の長い時間をかけて、明治大学のメンバーとして教育できることのメリットが、生徒にも、中学校・高等学校にも、そして明治大学にも実感できるような連携を目指していきます。
最後になりますが、校友、ご父母、教職員の皆さま、そして学生の皆さん、明治大学の紫紺の襷をより大きく、色鮮やかにして、未来に引き継ぐことができるよう、本年もご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
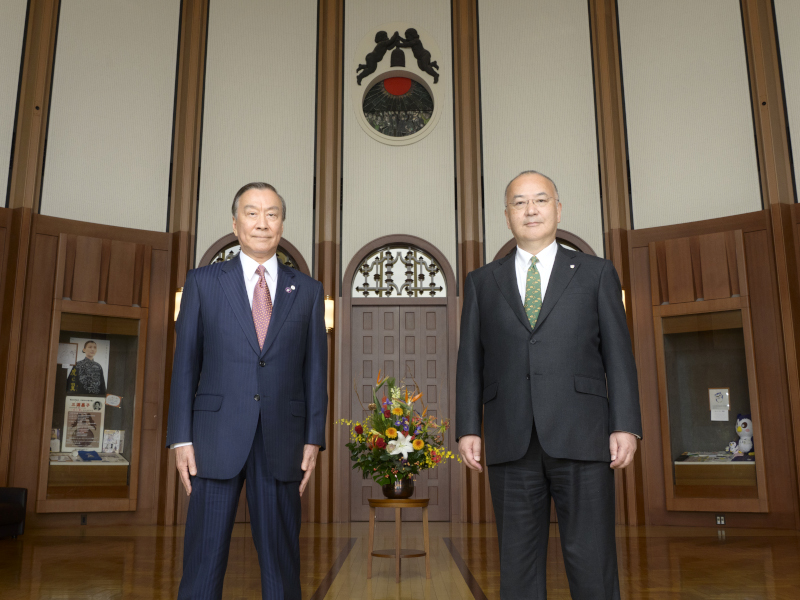
理事長 柳谷 孝
1975年明治大学商学部卒業。75年野村證券(現:野村ホールディングス)(株)入社。97年同社取締役、2000年同社常務取締役、02年同社代表取締役 専務取締役、06年同社代表執行役 副社長、08年同社副会長など歴任。16年5月より現職
学長 上野 正雄
1980年明治大学法学部卒業。92年司法研修所司法修習生。94年から9年間、裁判所裁判官として勤務。2003年法学部助教授、04年法科大学院法務研究科助教授、07年法学部准教授を経て10年同教授。副学長(広報担当)、学長室専門員長、法学部長など歴任後、24年4月より現職。専門分野は「犯罪学、少年法、犯罪者処遇法」
明治大学広報第793号(2025年1月1日発行)掲載