【M-Navi記者の学生団体取材】「生ごみは本当にごみなのか?環境問題へのアプローチ『コンポスト』に迫る!」
政治経済学部学生インタビューSDGsM-Navi記者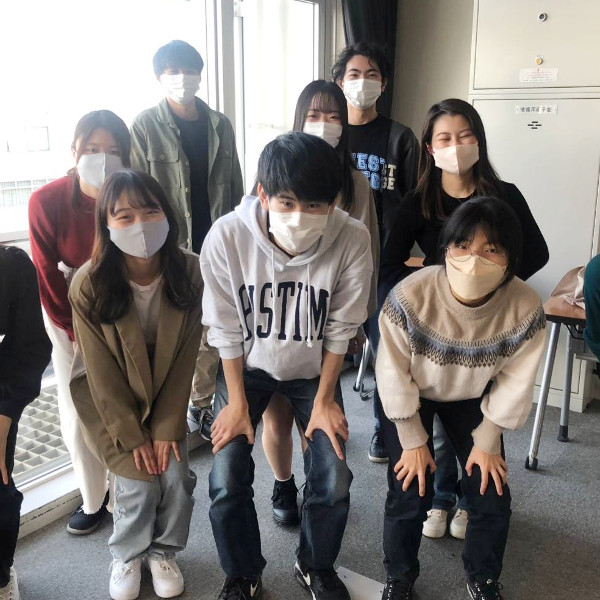
M-Naviプロジェクト「コンポスト」にインタビュー
第9回はM-Naviプロジェクト「コンポスト」(以下:「コンポスト」)を取材しました!和泉キャンパス「明大マート」横に並ぶ予定のパンジーのプランター。その土に含まれるのは、なんと食堂から出た生ごみです!「コンポスト」が取り組む、学生の環境問題へのアプローチに迫ります。
「コンポスト」って何?その苦労とパンジーについて
――活動内容について教えてください。
「コンポスト」代表 可児奈央未さん(以下:可児) 食堂から出る生ごみを利用して、堆肥を作る活動をしています。また、その堆肥を用いて和泉キャンパスにパンジーを咲かせる予定です。
――現在何人で活動されているのですか。
可児 1年次4人、2年次6人の計10人で活動しています。全員が政治経済学部で、環境経済学を扱った教養演習(政治経済学部で開講される少人数授業)を受講しています。
――活動の目標について教えてください。
可児 食堂から廃棄される食品ごみを少しでも減らすことです。食堂では食品ロスを減らす取り組みが行われていますが、野菜の皮などどうしても廃棄されてしまう部分があります。それらを土に返すことで、資源として循環させています。
――活動はまだ始まったばかりだとは思いますが、「コンポスト」というプロジェクトを作る過程や実際の活動の中で大変だったことはありますか。
可児 プロジェクトを一から立ち上げるということは初めての経験だったので、とても大変でした。初めてやることばかりで、どうして良いのか分からないながらもなんとか活動までたどり着くことができました。サポートしてくださった事務室の方や先生には本当に感謝しています。
小杉深優さん(以下:小杉) 活動を始めてから1カ月ほど経ちますが、実際にやってみると、事前の想定とは違うことが結構多いんですよね。想定とのずれをなくしていくことは難しくもありますが、同時にやりがいでもあります。
――想定外のことが起こったエピソードを具体的に教えてください。
小杉 本当は(生ごみと混ぜる)土をあまり濡らしてはいけないのですが、9月に台風が来て雨が続いた時、土を濡らしてしまい泥のようになってしまいました。土の水はけは、今後の課題です。
――やはり組織を一から作るということは大変なのですね。やりがいや活動していて楽しいと感じる時はどんな時ですか。
可児 この間、先日混ぜた土と生ごみを見てきました。野菜が少しずつ分解されるときの匂いがして、失敗していないということを実感し、すごくほっとしましたね。
――なぜパンジーを咲かせようと思ったのですか?
可児 元々、野菜を育てたいと思っていましたが、野菜は育てるのが難しいということと花が咲くときれいだということで、栽培が簡単だと聞いたパンジーを育てるという結論に達しました。
コンポスト(※)の設置場所が一般学生からは見えにくく、活動が周知されにくいと感じていました。そのため、みんなに見てもらえるように何かを育てようと思ったのが、パンジーを咲かせようと考えたきっかけです。
――パンジーについて調べたのですが、咲く時期は10月下旬から5月にかけてで、冬の間に咲くそうです。日当たりと風通しの良い場所で育てると良いそうですよ。
可児 パンジーのプランターは、和泉キャンパスの明大マート横の掲示板の下に置く予定です。事務室の方が勧めてくださいました。
――目立つ場所なので、パンジーが咲いたらとてもすてきですね。パンジーを咲かせるのはいつ頃を目指しているのですか。
可児 実現可能かどうかは分かりませんが、秋学期の授業が終わる前までに咲かせたいと考えています。
――パンジーが咲いたらぜひ見に行きたいと思います。最初に生ごみを溜め始めてからどのくらいで堆肥が完成するのですか。
可児 3カ月くらいかかると思います。結構時間がかかるんですよね。
――枯れ草などを溜めておくボックスのようなものを畑で見たことがあるのですが、コンポストはそれと似たものですか。
可児 同じです。
――そうなんですね。イメージが湧きました。
※コンポスト:「堆肥(compost)」や「堆肥をつくる容器や装置(composter)」のこと
なぜ「コンポスト」に?その理由ときっかけ
――M-Naviプロジェクトに応募したきっかけについて教えてください。
可児 私がごみ問題に興味があり、ちょうどM-Naviプロジェクトを見つけたことで組み合わせたいなと考えました。そこで、所属している環境経済学の教養演習に合うと思ってみんなに声をかけたら、たくさん集まってくれて実際にやることになりました。
――活動に対する学生からの反響はありましたか。
可児 活動が開始したばかりなので、他の学生からの反響はこれからですね。いろいろな人に「コンポスト」の活動について知ってほしいので、今度「土のかき混ぜ体験会」を行う予定です。来年度以降も活動を続けていきたいので、「面白いな」「楽しいな」と思ってくれる人を見つけたいですね。
――印象に残っているエピソードを教えてください。
篠原有希人さん(以下:篠原) 初日に行った土のかき混ぜが印象的でした。台風が近く、雨が降っていてとても大変でした。みんな初めてだったので、試行錯誤しながら濡れた土を頑張ってかき混ぜました。
――それは大変でしたね。なぜ「コンポスト」に入りましたか。
小杉 同じ教養演習の先輩から誘われたからです。プロジェクトをやると聞いたときはコンポストのことを知りませんでした。しかし、調べていくうちに、個人でも環境問題に直接貢献できることがあるのだと知り、「やりたいです」と言いました。
――コンポストに興味を持ったきっかけを教えてください。
可児 ものをごみとして捨てたくないという気持ちがあり、そこからコンポストに興味を持ちました。面白そうで実際にやってみたいと思い、祖母の家に生ごみを持参して埋めてみました。かぼちゃなどの芽が出てきてしまうこともあり、その成長を見るのも楽しいです。
メンバーと協力して完成させるコンポスト。そして環境問題への思いとは
――メンバーの魅力を教えてください。
可児 まず、篠原さんも小杉さんも環境問題に強い感心を持っていることが魅力です。篠原さんは自分で興味を持ったことを勉強しようという姿勢を持ち、実際に行動に移す積極性があります。小杉さんは自分で仕事を見つけて実行し、不確実なことがあればしっかり確認を取ってくれるので、とても頼りにしています。
小杉 可児さんと篠原さんは自ら問題を発見し、その解決方法をとてもよく考えています。コンポストや環境問題に関して深く考えられる数少ない場で、メンバー同士で意見交換ができることが魅力だと感じています。初めてコンポストを教えてくれたのは可児さんです。環境問題に関するセンサーがとても敏感で、企画を一から作り、それを中心になって進めている可児さんを尊敬しています。
――普段から環境問題へのアンテナを張り巡らせているのですか。
可児 環境問題へのアンテナというよりも、「もったいない精神」だと思います。家族もエコや節約が好きなので、もったいない精神の遺伝だと思っています。
――活動開始からの1カ月と活動への準備期間の中で学んだことを教えてください。
可児 特に学んだことは、団体の動かし方です。メンバーへの連絡や情報共有を忘れないようにしています。仕事の割り振りが苦手だったのですが、全部自分一人で仕事を終わらせず、仕事を割り振って、二人に頼りながらも皆で進めていきたいと考えています。
――すてきな組織の在り方ですね。仕事を割り振るコツはありますか。
可児 やるべき仕事を全て書き出しています。そして自分ができること、他の人に頼むべきことを分けるようにしています。やるべき仕事の範囲が定まっていると、お互いに作業がしやすく、相手にどの仕事なら取り組めるか聞くこともできます。
――環境問題やゴミに関する考え方の変化はありましたか。
小杉 自分にとって重要でありつつも、どこかふわっとしていた環境問題について学ぼうと考え、環境経済学の教養演習に入りました。そこでコンポストを知り、環境に対し個人でできる工夫として多様なアプローチの方法があることを学びました。環境問題に具体的にどのように取り組むかを考えるきっかけになったと感じています。
――具体的な生活の変化はありましたか。
小杉 食料廃棄について意識するようになり、今までは捨てていた大根の葉をお吸い物にしたりしています。
可児 キャベツの芯なども漬物にすると結構おいしいのでお勧めです。
篠原 普段の行動の変化としては、あまりビニール袋を使わなくなりました。鞄に詰めたり、エコバッグを使用するようにしています。
――生ごみに比べ、プラスチックのゴミの再利用は難しそうですね。これからの展望について教えてください。
可児 まずは「コンポスト」の成功が一番の目標です。半年で終わらせることなく、ぜひ継続させていきたいです。新しいメンバーも募集したいと考えています。
小杉 「その場限りでの環境に対する姿勢は良くない。継続してこそ環境問題に対するアプローチの一つになる」と教養演習の担当教員である大森正之先生がおっしゃっていました。その言葉通り、継続を目指して行きたいです。
可児 「コンポスト」設立にあたって、黒川農場で働かれている甲斐貴光先生にもご協力いただきました。お勧めの本を教えてくださったり、コンポストの発酵方法、企画書についてのアドバイスをくださいました。それまでは全く面識のなかった教授にもご協力いただき、とても感謝しています。
――明大生に向けて一言お願いします。
可児 生ごみは単なるごみではなく、工夫次第で良い肥料になるということをぜひ知っていただきたいです。メンバーを募集していますので、興味のある方はご連絡ください。
※M-Navi「コンポスト」メールアドレス:mnavi.compost@gmail.com
小杉 「コンポスト」のような活動があると知ることで、環境問題に対するアプローチとしてこのような方法があると知っていただくきっかけになればうれしいです。
篠原 数ある環境問題への関わり方の中で、それぞれにあった方法を見つけて参加していただければ良いなと思います。
――ありがとうございました。
M-Navi記者から~皆さんへのメッセージ~
守屋:生ごみが堆肥に変わり、パンジーを咲かせることができるコンポストのすごさにとりこになりました!M-Naviプロジェクトの大学イノベーション部門に応募されたと聞き、これからの活動が楽しみになりました!パンジーが咲いたら和泉キャンパスまで見に行きます!
坂倉:世界規模で展開される「環境問題」。それをより身近に捉え、試行錯誤を重ねながら実践していく姿に深く感心しました。パンジーが咲くのを心待ちにしています!
福森:環境問題への関心が高まる中、その場限りの企画ではなく、継続して携わり続けたいという方針に感動しました。
稲田:取材を通じてコンポストについて詳しく知ることができました。自分で取り組めることが身近にあると知り、実際にやってみたくなりました。
河内:私自身、畑に囲まれて育ってきたので、「コンポスト」の活動はどこか親近感が湧きました。今回の取材をきっかけに、個人の問題として環境問題を考えていきたいです。
山本:環境問題に対するアプローチは、私が知らないだけできっとまだまだたくさんあるのだろうと思いました!明大生にも「コンポスト」の活動をもっと知ってほしいです。
※記事中に掲載した写真は撮影時のみマスクを外すなどの配慮をしております
MEIJI NOWに出演いただける明大生の皆さんを募集しています。大学受験や留学の体験記、ゼミ・サークルの活動をMEIJI NOWで紹介してみませんか?
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです










 募集案内を見る
募集案内を見る

