
総合数理学部の先端メディアサイエンス学科で独自のゲーム開発に取り組む柴田光さん。学部の講義や研究室で学んだ「とにかく、まずは作ってみる」というアイデアを実現する力について伺いました。
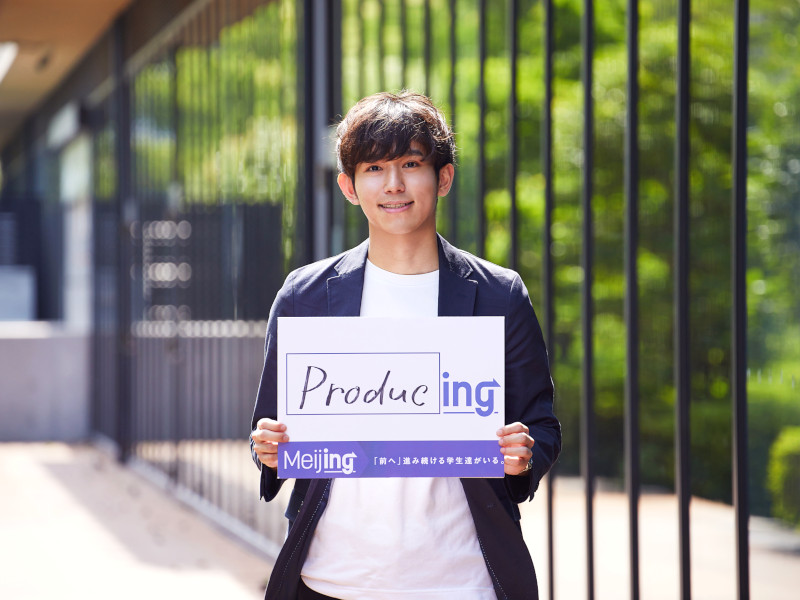
柴田さんのMeijingは、「作り出す」を意味する”Produc” ing
1年次の演習が、「ゲーム開発をもっとやりたい」と考えるきっかけに
入学前の総合数理学部 先端メディアサイエンス学科へのイメージを教えてください。
当初は「コンピュータに強くなれば将来の選択肢も増えるのではないか」という漠然とした考えしか持っていませんでした。しかし、入学前に学科長の宮下芳明先生から「人間の表現能力をコンピュータで拡張する」ためのさまざまな試みについてお話を伺い「ここなら自由で楽しい研究ができそうだ」と思うようになりました。
実際に入学してどのような講義を受けていますか。
印象的だったのは、1年次の必修科目として夏休み期間に実施されるEP(エンタテイメントプログラミング)演習です。この授業では、全員がProcessingというプログラミング言語を使ってオリジナル作品を制作します。入学後にプログラミングを初めて学ぶ人が多いですが、僕もその一人です。そのため、僕にとってはハードに感じる内容でしたが、だからこそ技術より発想力で勝負しようと考えました。
そこで制作したのが、ある情報番組に登場する目覚まし時計をモチーフにしたキャラクターを、「6時55分」になるまでにゴールさせることを目的とした、ジャンプアクションゲームです。
僕は、日常の何げないところからアイデアの種を常に探しているので、このアイデアも自分がたまたま番組を見ていた時に、6時55分になるとアナウンサーの話を遮って突然キャラクターが出てくる様子が面白いと感じたところから、イメージが膨らんでいきました。
先端メディアサイエンス学科の授業では度々プレゼンテーションの機会があり、EP演習でも最後に自分の制作物について発表する時間があります。オンライン上で100人以上の履修生がいる中プレゼンテーションに臨んだのですが、先生や他の受講生から「どうやって思いついたの?」と驚かれたり、笑ってもらえたりとうれしい反応を多くいただきました。授業が終わってからも「あのゲームの人だ!」と声を掛けてもらえたことは自信につながり、「ゲーム開発をもっとやってみたい」と考えるきっかけになりました。

先生との意見交換や先輩とのプロジェクトで鍛えられた発想力
3年次から所属している渡邊恵太研究室では現在はどのような研究をしていますか。
渡邊研究室の研究テーマは、テクノロジーと人の環境を融合させるための「インタラクションデザイン(※)」です。僕はその中でも、ゲームによる人々のつながりに関する研究を行っていて、個人研究と複数人で取り組むプロジェクトでそれぞれゲーム開発をしています。
※インタラクションデザイン:ソフトウェアやサービス上でユーザーとオーナーの間に双方向のコミュニケーションを生むデザインのこと
これまでに開発されたゲームについて教えてください。
個人研究では、「なまえ宝探し」というゲームを作りました。3Dのマップ内に散らばったひらがなの中から覚えたい名前の文字を一文字ずつ探していくシンプルなゲームで、制作の発端は「ゲームを通じて楽しく名前を覚えられないか」と考えたことでした。これは、僕自身、初対面の人たちとアイスブレイクのゲームをする時に、相手の名前を覚えられないまま、ただゲームをしただけで終わってしまうことがよくあったことから着想しました。
渡邊研究室では、研究に入る前にまず、研究したいテーマ自体について渡邊先生との意見交換のラリーを何往復も行います。僕自身が実現したいアイデアである「楽しく遊んでいたらいつのまにか名前を覚えていた」というゲームが、渡邊先生が研究されている「日常に融け込めるようなシンプルな手法」にできるよう、何度も丁寧なフィードバックをいただきました。
また、研究室ではまずプロトタイプ(試作品)を作ることが大事にされています。僕もとにかく、まずは作ったものを試していただき、フィードバックをいただくことを繰り返しました。3年次で一度完成させたものの、今もさらなる改良を続けています。
 個人研究で開発した「なまえ宝探し」
個人研究で開発した「なまえ宝探し」複数人で取り組むプロジェクトでは「Open Video Game Library(OVGL)」というチームで「研究者のためのビデオゲーム」を作りました。ゲームは、新しい触覚装置の研究や心理学実験などさまざまな分野で利用されています。しかし、市販のゲームは著作権などの問題で自由に使用できないケースが多いという問題がありました。そのため、コードを公開して誰もがアクセスできるようにすることで、実験や研究に用いやすいゲームを開発しました。
プロジェクトのメンバーには、研究室の大学院生も含めた先輩もいます。学会発表をするためのスケジュールの立て方などを丁寧に教えていただいた他、先輩方の研究の視点やスピード感を学びました。
 OVGLで開発した「研究者のためのビデオゲーム」。コードを公開し誰もがアクセスできるようにしている
OVGLで開発した「研究者のためのビデオゲーム」。コードを公開し誰もがアクセスできるようにしているこれまでの学生生活で学んだことや得たものを教えてください。
発想力へのこだわりは、この4年間でより強くなったと感じます。研究室では、「生活に融け込むコンピュータのデザイン」を重視していて、アイデアを考える時にも「どうすればそれを実現できるのか」を意識するようになりました。渡邊先生からフィードバックをいただきラリーを重ねる中で、一つのものを作るにしてもさまざまなアプローチでアイデアを出す力が鍛えられました。
また、研究室に所属する前の面談で学科長の宮下先生から「アイデアは数で勝負。方針が決まれば後は加速するだけ」と言われたことが印象に残っています。
アイデアはとにかくまず数を出すことが大切で、数を出すことで大勢にハマる面白いアイデアが分かってくる。それが見えたら「もっとこうしたい」という欲がどんどん出てくる。宮下先生はこの「加速」の部分がものづくりで一番楽しいとおっしゃっていました。いつも楽しみながらものづくりをされている宮下先生の言葉はとても腑に落ちて、僕も今まさにこの言葉を実践しているところです。

高校生の皆さんにメッセージをお願いします。
僕は漠然とした興味関心から進学先を選びましたが、いざ入学してみると一つの学部・学科でもさまざまな研究をしている先生がいるので、興味関心の幅がどんどん広がっていきました。それらの学びが一つずつ自分の中でつながっていって、自分が進みたい道が見えてきました。
今大学で何を学ぶべきか悩んでいる方は、まずは「自分が楽しいと思うこと」は何か、じっくり考えてみてください。それがきっかけになって、入学後に選択肢が広がっていくと思いますよ。
 キャンパスではさまざまな出会いがある
キャンパスではさまざまな出会いがあるMeiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです







