
朝3時半に起きて朝練に向かい、夜10時に帰宅した後に論文を読む……部活と研究の両立のためにハードな生活をこなしながらも「自分のやりたいことがどちらも続けられて、うれしい!」と笑顔を見せる白田藤子さん。農学部での研究や、箱根駅伝を目指して活動する体育会競走部マネージャーとしての挑戦について聞きました。
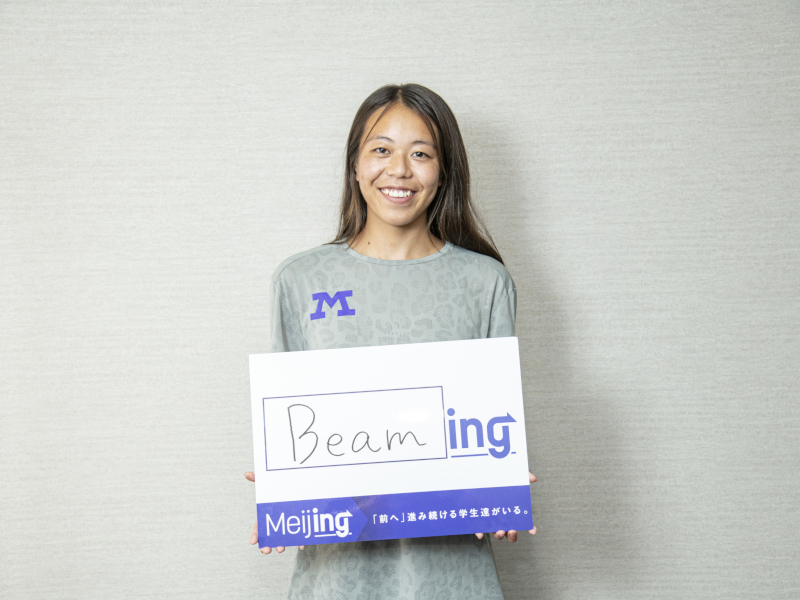
白田さんのMeijingは、「自分のやりたいことで輝く」という思いを込めた“Beam” ing
「トマト愛」から始まった研究への道
農学部に興味を持った理由を教えてください。
幼い頃からトマトが大好きで、今でも2日で3kgの箱詰めを食べきってしまうほどです。トマト好きが高じて、まずは植物に自然と興味が湧きました。その後、「おいしいトマトを作ってその魅力を広げていきたい!」という思いから、農学を学びたいと思い、大学選びを始めました。
その中で明治大学を選んだ理由を教えてください。
最初は品種改良について学べる大学を調べていたのですが、イネなど穀物の研究が中心となっているところがほとんどでした。その中で、明治大学農学部のホームページのトップが野菜の写真だったんです!詳しく調べてみると、野菜を扱う分野が充実していて研究が深められそうだと思いましたし、履修が自由な部分が多いことにも魅力を感じ、明治大学が良いなと思いました。
 農場で作業をする際の作業着での一枚
農場で作業をする際の作業着での一枚「品種改良」の異なるアプローチに、野菜への興味が深まる
印象に残っている授業はありますか?
2年生のころに受講した「基礎植物育種学」と「バイオテクノロジー」の二つです。
「基礎植物育種学」は品種改良をテーマにした授業なのですが、交配の仕方は複雑で、ただ組み合わせれば良いというわけではありません。異なる品種同士を交配して得られた新しい特徴を持つ種が、既存の種と異なることを証明するために確認を繰り返さなければいけません。その作業には10年以上かかると学び、「おいしいトマトを作りたい!」と簡単に考えすぎていたな……と少し反省しました。
「バイオテクノロジー」は、育種学のように植物を地道に交配して品種改良をするという方向性ではなく、植物体がもつ遺伝子そのものを操作し、新しい品種や病害に強い品種を作る、その方法をテーマにした授業でした。技術の開発は進んでいる一方で、倫理的な問題から農業にすぐに取り入れられるわけではありませんし、認証や販売表記の問題にもつながると知りました。この2つの授業を同年度内に受講したことで、一口に「品種改良」といってもさまざまな方法や課題があると学べたことは魅力的でした。
どちらも専門的な内容で難しく、授業についていくのは大変でしたが、授業終わりに質問すると、どの先生も丁寧に教えてくださりました。黒板いっぱいに説明してくださる先生もいらっしゃって、自分の理解が深まったと感じています。

競走部と研究の両立を目指して。希望の研究室で野菜の研究に関わる
所属している研究室と、その研究室を選んだ決め手について教えてください。
野菜園芸学研究室に所属しています。元々しっかりと研究がしたかったので、高校生の時から大学院への進学を希望していました。その中でも「現場直結型」をモットーに野菜に関しての幅広い研究を行っているこの研究室にとても魅力を感じました。
私は体育会競走部のマネージャーを務めていたことから、研究との両立に不安もありましたが、野菜の研究に関わることをブレない目標に、積極的に研究室への訪問を重ね、希望の研究室に受け入れていただきました。先生には、時に競走部の活動の相談にも乘っていただきながら、何よりも手厚く研究活動のアドバイスをしていただいています。また、現在は、植物の生育阻害活性を軽減するための農業用資材を企業様と共同開発・改良し、生産現場への普及を目指す研究にも携わっています。
本気で頑張る選手たちをサポートする人になりたい、という思いで入部した競走部
競走部に入ったきっかけは何でしたか?
元々長距離をやっていて、大学に入学してサークルを探している中で、たまたまSNSで競走部のマネージャーを募集していることを知り、見学に行きました。グラウンドで自分が経験してこなかった高いレベルで本気で箱根駅伝を目指して走っている選手たちを見て、圧倒されました。私自身、高校生の時にマネージャーの存在に救われた記憶が蘇り、「この人たちのサポートをしたい!」と、その日のうちに入部を決意しました。

マネージャーのリーダーである「主務」を目指して
寮に住まない学生としては初めて、運営業務の統括をする「主務」という立場についたと伺いました。
競走部では、選手がマネージャーに転向して主務になるというのがこれまでの慣例でした。主務は選手や監督とも積極的にコミュニケーションを取る必要があり、寮に住まない学生、つまり「通いのマネージャー」では務まらない、と言われたこともありました。しかし、私たちの代はマネージャーの数も多く、1年生の時から「選手は選手のまま、4年間走り続けてほしい」という思いが強かったため、通いのマネージャーだけで運営する方法をずっと考えていました。
2年生の終わりに、監督にそのような考えを直訴しました。「3年生の1年間で自分たちだけで運営できる自信を持てるようにしよう」と背中を押していただき、主務になるための1年間がスタートしました。朝は5時20分に集合して朝練があり、日々情報を共有することが大切です。監督からは「毎日来なくても良い」と言われましたが、自分でやると決めたことですし、「通いでは務まらない」と言われるのが悔しかったので、日々の行動で示すしかないと思っていました。
先輩につきっきりで仕事を教えてもらい、同期や後輩のマネージャーに沢山支えてもらったおかげで、4年生になった今、主務を任せていただくことになりました。
さまざまな挑戦が「ブレない自信」に
競走部での活動を通じて成長したと感じることは何でしょうか。
マネージャーを経験して感じたのは、実際にグラウンドに出て選手をサポートする以外にもやらないといけない仕事が多いということです。
練習前の準備や、試合情報のキャッチアップ、試合に出場する選手のエントリー、移動手段や宿泊場所の手配、大学への申請……。仕事が突然降ってくることも多く、下級生の時には、遊園地で遊んでいる最中に、部の航空券の手配をしたこともありました(笑)
主務になると決意してから、それを実現するために何をしたら良いか考えて形にしてきました。「やる」と決めたことに対して、さまざまな感情に負けずにやり続けて今主務を務められている、その過程が自信になっています。自信を持ってこの部の運営の中心に立てている、というのは大きいですね。
研究とマネージャー業の両立は大変ではありませんか?
朝3時30分に起きて、10km先のグラウンドに自転車で向かい、授業と部活が終わって家に帰るのは夜の10時ごろ。その後の時間を、家事や論文を読む時間などにあてています。
両立しようとした結果、たしかに余裕はなくなってしまったかもしれません。それでも、「やりたい」と思って始めたことを続けられる環境にいさせてもらっているので、ただただうれしいですし、感謝の気持ちでいっぱいです。研究と部活、どちらもやりたいことだからこそ頑張れています。

今後は研究に没頭して研究職を目指したい!
将来のビジョンを教えてください。
将来は研究職に就きたいです。元々細かい作業やコツコツと積み重ねることが得意で、競走部で培った体力・継続力には自信があります。今ある農業の知見をより生かす、あるいはより現場への普及を実現するような、有用性のある研究を重ね、農業の課題と向き合いたいと考えています。
大学は全力でチャレンジできる場所
最後に、高校生へのメッセージをお願いします
大学はやりたいことを実現しやすい、チャレンジしにいける場所・期間だと思っています。将来やりたいことがある人はどんどんチャレンジしてほしいですし、やりたいことがない人は、将来やりたいことを探す時間にあてられる期間だと捉えるのも良いかもしれません。
受けた授業や、大学生活で関わった人によって視野が広がることもあります。将来について悩める「贅沢な時間」だと思って過ごしても良いと思います。結果の良し悪しだけで終わらないような「過程」を生み出せるように私も皆さんと一緒に頑張りたいです。応援しています!


Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです







