
「将来は和歌山県知事になりたい」――そんな思いを抱いて政治経済学部地域行政学科に入学した前冬磨さん。政治の道を志したきっかけや、大学生活を通じて学んだ「理想を実現する難しさ」について聞きました。

前さんのMeijingは「自分の夢を貫く」という思いを込めた“Dream” ing
高校生の時の和歌山県知事に憧れて、政治経済学部へ
将来の夢は「和歌山県知事」だと伺いました。きっかけを教えてください。
2021年に和歌山県で全国高等学校総合文化祭(※)が開催されたのですが、僕はその生徒実行委員長を務めていました。そのときに実行委員会の名誉会長だった仁坂吉伸元知事に憧れを抱いたのがきっかけです。
高校2年生の時、仁坂さんから「今回のコンセプトを説明してみろ」と言われました。頑張って説明しようとしたものの、要領を得ない説明をしてしまいました。それを聞いた仁坂さんは「その説明はリーダーにふさわしくない」とおっしゃったんです。「リーダーとしてやっていくなら、大会にまつわることならいつ何を聞かれても答えられるようにしておきなさい」とお叱りを受けました。この出来事がきっかけでリーダーに必要なことは何なのか、常に自分の頭で考えて行動するようになりました。
一方で、僕がプレ大会で全体挨拶をした際には最後まで聞いてくださって、「素晴らしかった。本大会で会えるのを楽しみにしているよ」と声をかけていただきました。物事一つ一つに真剣に向き合ってくださる姿に感激しました。
(※)全国高等学校総合文化祭:全国の高校生が芸術文化活動の成果を発表する文化祭。毎年各都道府県持ち回りで開催

「誰かのルーツである場所」を守りたい
そこから具体的に政治に関心を持つようになった理由はありますか。
僕は和歌山県の有田川町というところの出身で、小学校の同級生が20~30人しかいない田舎です。漠然と「この町はこのまま続いていくんだろうか」という不安を感じるようになりました。和歌山県内でいえば、和歌山市以外のほとんどは過疎化が進んでいる地域です。自分が生まれ育った町、誰かのルーツである場所を守れる人でありたいと思うようになりました。
明治大学の政治経済学部を選んだ理由を教えてください。
地域行政学科という地方行政に特化して学べる学科があったことが決め手です。政治全体のことを学べるところはたくさんありますが、地方の人や生活に寄り添ったところで政治はどのようにあるべきか、ということを勉強していきたいなと思っていたので、大学のパンフレットを見たときに「ここを受けてみたい」と思いました。現在は、学科長でもある牛山久仁彦先生のゼミナールに所属し、日々白熱した議論を交わしながら鍛えられています。
賛否が分かれるような問題にも向き合う力を鍛えたゼミでの経験
ゼミナールを通じて成長したことはなんでしょうか?
何事に対しても自分の意見を分かりやすく伝えることの大切さを学びました。
さまざまな問題について、「いろいろな見方があるから、どちらか結論は出せないよね」というようなポジションを取るのって、すごく簡単だと思うんです。けれど、大学での学びを経て、それでは僕がなりたいリーダーにはなれないと気づきました。広く意見を聞いたうえで、どちらかの立場に立つことも大事で、自分の意見を言わないと何も始まらないですよね。
これは多分、自分が政治家になった時も必要な要素だと思っています。自分でよく分かっていないような、あいまいなことを言わない、そして逃げない。自分の意見をしっかり持ち伝えていくという力は、今もゼミを通じて身に付けている途中かなと思います。
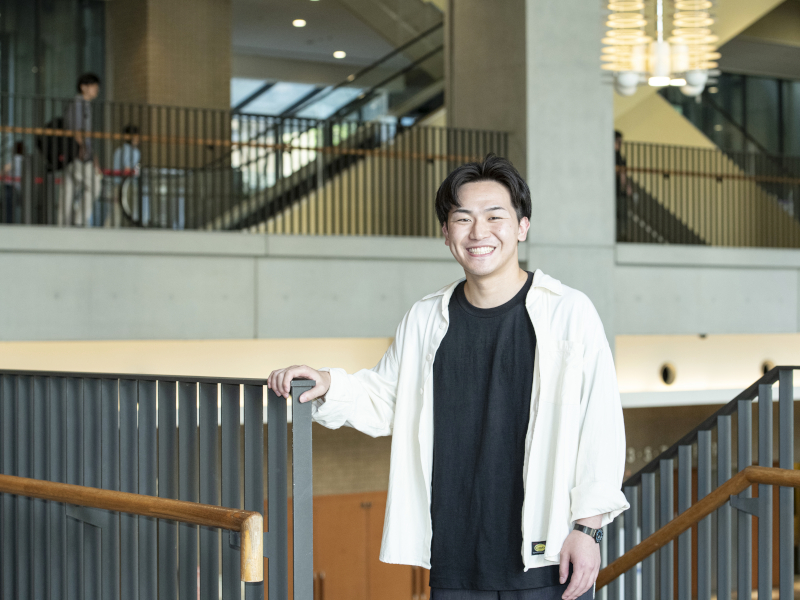
印象に残っている授業を教えてください。
3年生の時に受講した「応用総合講座B」というさまざまな自治体の首長の方のお話が聞ける授業です。特に印象に残っているのは茨城県境町の町長の方がゲスト講師として登壇した回です。
新しく何かを始めることの難しさについて語られていました。「行政の失敗は許されない。けれど、その中でいかに新しいことに挑戦して町としての強みを作っていくかが重要。踏み出す一歩を持っているかどうかが10年後、20年後の人々の生活に直結する」というようなお話を聞いて、僕も賛否が分かれるような問題でも逃げずに向き合い、その地域の将来を見据えて変革を起こせるような首長になりたいと思いました。
当時、明大祭の実行委員長を務めていて、自分がやっていることが本当に正しいのかと葛藤していた時期でした。そんな中でこの授業を受けたことが大きくて、実際に自分の憧れるような人たちが、葛藤を抱きながらも突き進み続けている姿にリスペクトを持ちましたし、自分もこうあり続けないといけないと感じました。
リーダーとして周りを巻き込む“人間としての魅力”の大切さを実感
明大祭実行委員会での活動を教えてください。
2年生の時に、「渉外局界隈部門」という主に外部の方々との交渉を担う部門の部門長を務めました。その時、コロナ禍明け初めての「明大前サマーフェスタ&盆踊り」の運営に携わったことは印象に残っています。
部門長として感じたのは、「チームで作り上げること」の大切さです。これまでは、どちらかというと「自分が頑張ればなんとかなる」というパワープレーで物事を進めるタイプでした。しかし、今回のようなイベントでは関わる方々の範囲が広い分、自分の下について動いてくれる人々を信じて任せていかないと進められません。
いろいろな立場の人を巻き込んでいくための“人間としての魅力”を身に付けていかないといけないなと感じました。

3年時には450人を束ねる実行委員長も務めたと伺いました。
素直に言うと、僕が1年間委員長としてやったことを、「良い」と捉える人もいれば、「良くなかった」と捉える人もいると思います。「みんなにとって良いこと」を作るのは難しいなと学んだのが、この最後の学園祭の1年間だったかなと思います。
コンセプトに掲げていたのは「あらゆる人の期待を超えた新たな明大祭」です。これまでの明大祭は、どちらかというと「学生のためのお祭り」という部分が強くて、地域の人や外部の方との関わりはあまり多くない印象でした。「明治大学」は、みんなから憧れを持たれ、愛されている大学だと思います。にもかかわらず、「明大祭」はまだその域に達していないのではないか、と感じていました。
駅を出た瞬間から空間的に連続している学園祭を作りたいと思い、京王電鉄さんのご協力を得て、期間中は明大前駅の看板の隣に「明大祭駅」という看板を設置させていただきました。駅から和泉キャンパスに行くまでの道は商店街の皆さんに露店を出してもらうなど、盛り上げていただきました。その他にも、地域と一体となった新たな企画を計画・実施しました。
明大祭が終わった後、地域の方から「ここまで町と大学が融合している学園祭は初めてだね」と声をかけてもらいました。元々、学生だけではなくて、その周辺にいる人たちに愛される学園祭を理想としていたので、とてもうれしかったです。

 明大祭で制作したステッカー。実行委員のメンバーの思いとアイデアが詰まっている
明大祭で制作したステッカー。実行委員のメンバーの思いとアイデアが詰まっている将来、「変革を起こすリーダー」になるために、経営的視点を持ちたい!
卒業後はメガベンチャーに就職?
これは就職活動でも言っていたことなのですが、「民間企業で働くのは10年」と決めていました。その中でどれだけ成長できるか、が就職活動の軸でした。大手だとスキルを身に付けるには短すぎるし、ベンチャーでは何ができるのか未知数、その中で出した最適解がメガベンチャーへの就職でした。
自治体に勤めて首長を志す道もあったとは思います。ただ、僕は「変革を起こせるリーダーになりたい」と思っているので、目指すリーダー像を考えたときに、その道ではなく、民間の経営的な視点があった方が良いのではないかと思いこのキャリアプランを選びました。
「人任せにしない」という意志が芽生えた
明治大学で学んだことで、政治への思いに変化はありましたか?
学ぶ前は、「誰かがやってくれるだろう」という思いが少なからずありました。例えば、「生まれ育った町を守りたい」と僕は言いましたが、突然、和歌山県がなくなることはないし、「あと100年ぐらいあったら、もしかしたらすごい人が出てきて、和歌山県が良くなるかもしれない」と思ってもいました。でも、この4年間勉強して今に至るまでで、誰かじゃなくて、自分がやらないといけないと思うようになりました。「人任せにしない」という意志が芽生えたということですね。

実りある4年間を作れるのは自分だけ!
最後に、高校生へのメッセージをお願いします
実りある4年間を作れるのは自分しかいません。自分の中での目標を掲げ生活して、「意味があったな」と思って卒業できるのが一番だと思います。まずは、今行きたいと思う大学に向けて自分ができる最大限の努力をしてほしいです。入学後は打ち込めるものを見つけて、そこで頑張っていたら、きっと毎日が楽しくなるはずです!
Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです







