
「食」という側面から人を支えようと農学部へ進学した原田さん。3年次からは農作物に寄生する線虫の研究を始めました。さらに研究活動だけでなく、タイへの留学中に模擬国連を経験するなど、プレゼンテーション能力も磨いています。「前へ進むこと」を大切に努力し続ける原田さんに、農学部での研究や留学での学びを伺いました。
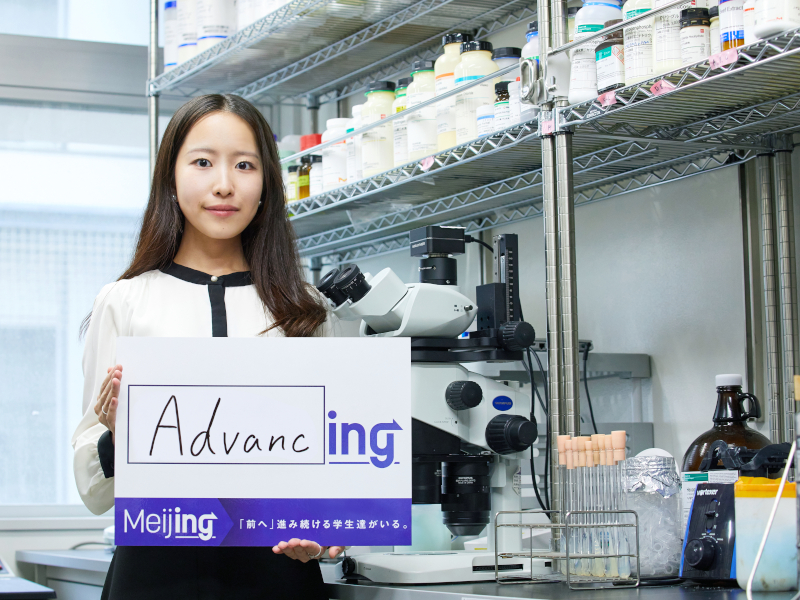
原田さんのMeijingは、「前進する」を意味する”Advanc” ing
入学して気付いた「農学」の多様さと面白さ
農学部に入学した理由を教えてください。
私は「人の人生や生命を支えられるような人であること」を人生の目標としています。農学部を選んだのは、生きる上で欠かせない「食」という側面から人を支えるための学びが得られると考えたからです。また、私は幼い頃から生物が好きで、生物に関する実験や研究ができる環境で学びたいという漠然とした思いも持っていました。
入学してみて感じた、農学部の魅力はありますか?
「農学」と言えば畑を耕して作物を育てるイメージが強かったのですが、1年次にさまざまな入門講義を受講してもっと幅広い学問なのだと気付きました。多様な分野の先生から授業を受けたことで、例えば害虫や病気など農業問題における課題や農村の管理・デザインについて学ぶことも農学だと知りました。明治大学では、まず「農学」という大きなフィールドについて学べること、そしてその中で自分の興味関心をじっくり探ってから専門分野に進めるところが魅力だと感じています。

研究活動に没頭できる環境で「線虫」の研究をスタート
3年次から新屋良治准教授の植物線虫学研究室に所属されていますが、研究室を選んだ理由を教えてください。
私が大学生活の中で特に力を入れたいと思っている研究活動に邁進できる環境だと感じたからです。入学前からホームページを見ていて、「線虫」という生き物自体を研究している研究室は珍しく、興味を持っていました。そこで1年次に研究室を訪問したところ、教授や先輩が研究内容について丁寧に教えてくれたり、「研究が楽しい」と話してくれたりして、ここで学びを深めたいという気持ちがますます強くなりました。

現在は、どのような研究をされているのでしょうか?
植物寄生性線虫の一つである「ネコブセンチュウ」の孵化プロセスについて研究しています。このテーマを選んだのは、2年次の授業で農業害虫としてネコブセンチュウが多くの食料に被害をもたらしていると知ったことがきっかけです。ネコブセンチュウの研究が、食料を守ること、ひいては人の命を守ることにもつながると考えました。
今は、線虫を感染させるために育てていた植物が育ち、実際に感染させたところです。生物を扱う研究なので思い通りにならないこともありますが、同じ分野を研究する先輩からアドバイスをいただきながら進めることができています。大学院進学も見据え、これから本格的に研究活動に取り組んでいきたいです。
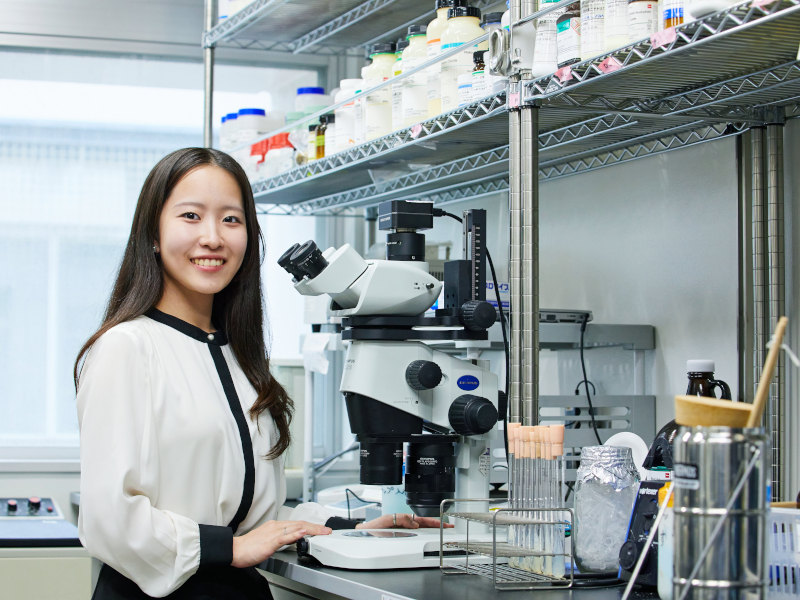
タイへの留学を経験し、「プレゼンテーション能力を高めたい」と考えるように
2年次に農学部の「国際農業文化理解プログラム」でタイに留学されたと聞きました。参加のきっかけを教えてください。
高校生までに何度か留学を経験したのですが、大学では語学を学ぶ以外の目的で海外に行ってみたいと考えていました。中でも「国際農業文化理解プログラム」の、農業を学ぶ立場として留学できるところと、国連の会議を模して、国際的に解決すべき課題を討論するプログラム「模擬国連」に参加できるところに引かれました。私自身、国連の仕事に興味を持っていた時期があり、高校時代から参加したいと考えていたためです。
書類選考や面接などを受けた結果、参加できることになり、一週間ほどの期間タイで学ぶことができました。プログラムでは模擬国連のほか、明治大学と協定を結ぶタイの大学を訪問して交流する機会もありました。
模擬国連では具体的にどのようなことを行ったのでしょうか?
模擬国連では、大学ごとに少人数のグループを作り、一国の大使となってその国の解決すべき課題や課題解決の方法を発表しました。私のグループはモルディブ代表として、主要産業の漁業におけるフードロス問題について取り上げました。資料を探したりプレゼンテーション用の言い回しを考えたり、タイの学生たちとお互いに母国語ではない言語で質疑応答などをするのは大変でしたが、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を鍛えることができたと思います。

留学を通して成長したことや変化したことはありますか?
留学中にプレゼンテーションがとても上手なタイの学生に出会い、刺激を受けました。彼は海外も含めてこれまでさまざまな場でプレゼンテーションをしてきたそうで、「私もとにかく場数を踏もう」と、今は友人の前で練習するなどして経験を積んでいるところです。
私は人と関わることが好きなので、今後も人前で話す機会を増やして、学会発表にもチャレンジしたいと思っています。そうした場で話す時に自分の伝えたいことを100%伝えるためにもプレゼンテーション能力は重要だと考えているので、今後も力を磨いていきたいです。
「とにかく前に進むこと」で、道は開ける
原田さんが大学生活の中で大切にしている考えや価値観はありますか?
自分の思い通りにならない時でもまずは前に進んでみることが大切だと考えています。そう考えるようになったのは、「自分が動かないとどうにもならない状況」を昔からさまざまな場面で経験してきたからかもしれません。
例えば中学時代、カナダへ一人で留学した時に現地で迷子になったことがありました。タクシーの呼び方もわからず途方に暮れましたが、自分でなんとかしなければと日本人の方を探して助けを求め、乗り切ったことがあります。また、皆がやりたがらない役割を「誰かがやらないと話が進まないし、やってみよう」と立候補して引き受けたこともありました。こうした経験の積み重ねが、今の自分につながっています。
最後に、高校生の皆さんへメッセージをお願いします!
進路に悩んだ時は、小さい頃から好きなものや得意なこと、大事にしてきた価値観を思い返してほしいです。そうした自分の軸は大人になっても案外変わらないもので、迷った時の指針になってくれます。またこの先、努力をしても自分の思い通りの結果にならないことがあるかもしれません。私は、それでもまずは前に進むことが大切だと考えています。その時は不本意な結果だったとしても、努力したことはきっといつか良い形になって皆さんの元に返ってくるはずです。応援しています!

Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです







