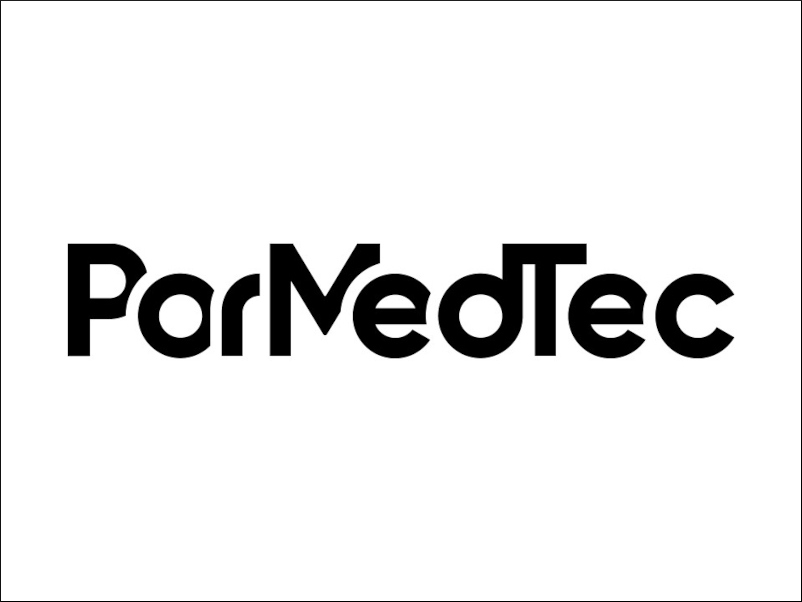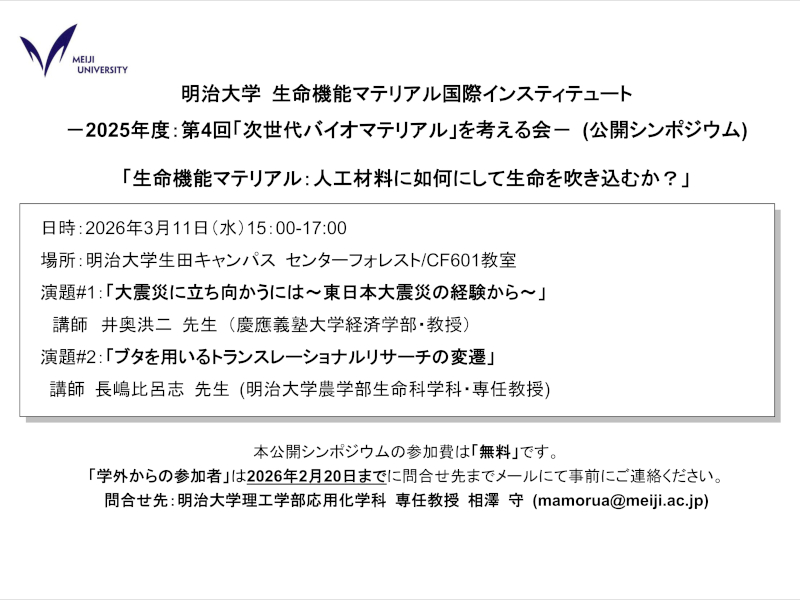関根氏の講演の様子
関根氏の講演の様子生命機能マテリアル国際インスティテュート(研究代表者=相澤守理工学部教授)は、3月5日に生田キャンパス第二校舎で、シンポジウムを開催し、約30人の学部生・大学院生・一般希望者などが聴講した。
シンポジウムは同インスティテュートが研究クラスターだった2018年から次世代バイオマテリアルを考える会として毎年開催されてきたもの。近年では「生命機能マテリアル:人工材料に如何にして生命を吹き込むか?」と題して企画され、この日は2023年度3回目の開催となった。東京工業大学物質理工学院材料系の生駒俊之教授と日本原子力研究開発機構物質科学研究センターの関根由莉奈研究員を招き、2つの講演が行われた。
生駒教授は「バイオセラミックスを活用したマテリアルセラピー」と題して講演。外部刺激に応答するナノ粒子の活用を通じて放射線や光照射による腫瘍組織の治療などの研究事例を紹介した。
関根氏は、「凍結凝集層中での化学反応を利用した新規材料合成と応用展開」と題して講演。地球上に900億トンも存在する木質成分セルロースをもとに、凍結プロセスを利用したカルボキシメチルセルロースの微細構造制御によって成功した、新しいハイドロゲルの生成について報告した。
インスティテュート代表の相澤教授は、「熱意が原動力となって研究を進められているということが伝わってきた」と述べ、シンポジウムを締めくくった。