
明大生が、所属するゼミ・研究室を紹介する「ようこそ研究室へ」。今回は文学部の猿田さんと細沼さんが、川島ゼミナールを紹介してくれます!

ゼミ概要紹介
川島ゼミでは、「自傷・自殺予防」「医療心理学」「病気と健康」などを研究テーマとしています。人や社会が抱えるさまざまな課題や困難に対する臨床心理学的アプローチについて、学術論文の講読、仲間との意見交換、臨床現場でのフィールドワークなどを通して学びを深めています。4年次には各自が臨床心理学的意義を追求した研究を行い、卒業論文を執筆します。病気や健康、生や死について考えながら、社会で生き抜く力を養っていくことを目指しています。
川島ゼミではこんなことを学んでいます!
3年次の春学期のゼミでは、3~4人のグループに分かれ、「ギャンブル依存」「自殺と自傷」「自殺予防ゲートキーパーに求められる知識とスキル」など、それぞれが興味・関心のある分野を選び、論文や資料をまとめ、発表やディスカッションを通して理解を深めました。秋学期は論文を読み解く上で必要な心理統計学の知識を復習しながら、それぞれの卒業論文に沿ったテーマで個人発表を行います。そして4年次では、研究計画の立案、調査の実施、データ解析を行い、関連論文を読み込みながら卒業論文を完成させます。
 普段のゼミの様子
普段のゼミの様子アピールポイント
何よりのアピールポイントはゼミの雰囲気です。毎週、穏やかな雰囲気でゼミが行われています。川島先生も温和な人柄で、伝わる言葉を選んでゼミ生に指導してくださいます。上級生も優しい方が多いので、交流の場では研究の話以外にも大学院進学や就職活動の話などを伺うことができます。今年の夏は、表参道のビルの屋上を借りて3・4年生合同のバーベキュー交流会を開催しました。
また、例年、コミュニティにおける心理臨床実践を学ぶために、学外の医療・福祉・矯正施設などに見学に行っています。今年は東京少年鑑別所で、3・4年生合同で見学実習をさせていただきました。
 2024年の見学実習での一枚
2024年の見学実習での一枚※東京少年鑑別所から許可を得て写真を掲載しています
ゼミの雰囲気
とても和やかな雰囲気です。毎週、授業の冒頭で、直近1週間で心に残った出来事を、先生も含めて各自1分程度で話すアイスブレイクの時間があったり、先生の出張のお土産をみんなで食べたりと、「ココロ」を扱うゼミならではの、安心して落ち着いて意見を出し合える雰囲気作りが大切にされています。夏のバーベキュー交流会では、買い出しや料理などを3・4年生全員が協力し合って進めるなど、自然に助け合うことのできる人たちが集まっている印象です。
 3・4年生合同のバーベキュー交流会での一枚
3・4年生合同のバーベキュー交流会での一枚先生の紹介
川島義高先生
川島先生は、「自殺予防」「医療心理学」「専門職連携教育」「支援者支援」「心理職の成長モデル」に関する研究をされています。穏やかな性格である一方、サッカーやダンス、ダイビング、フルマラソンなどの経験があり、アクティブな一面もお持ちです。ゼミ生同士の交流の場を積極的に設けてくださる先生です。
私はこんな理由でゼミを選びました!
猿田さん SNSと自殺の関係性に興味を持ったことが理由です。私自身、大学生になってからX(旧Twitter)を利用し始めて、SNSを使う時間が大幅に増えました。その情報量の多さと影響力の大きさから、SNSが人の精神状態にさまざまな好影響・悪影響を及ぼしていると感じ、詳しく研究したいと考えて川島ゼミを選びました。また、1年次も川島先生のゼミを履修していたので、卒業論文執筆の際にも川島先生から統計についての助言やフィードバックをいただきたいと考えました。
細沼さん 高校時代に不登校の同級生がいた経験があり、彼らがどのような困難を抱えているのかを知りたいという気持ちから、臨床心理学専攻に進学しました。川島ゼミを選んだ大きな理由は、自殺予防に興味があったからです。1・2年次のゼミで、若者の死因の第1位が自殺だということを知り、川島ゼミでその原因や対策を学びたいと思いました。また、川島先生はデータ解析にも詳しいため、卒業論文の執筆に必要な統計調査について、アドバイスをいただきたいと考えたことも理由の一つです。
川島ゼミあれこれ
人数
18人(3年次:13人、4年次:4人、博士前期課程2年次:1人)
OB・OGの主な進路
公務員、医療機関、社会福祉施設、広告代理店、情報通信業、放送番組制作会社、大学院進学など
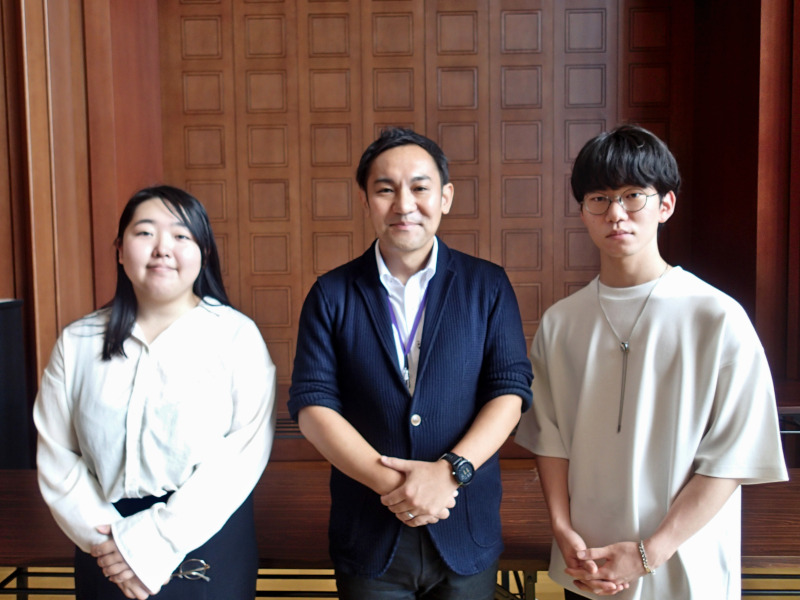 紹介者(写真左から)細沼さん、川島先生、猿田さん
紹介者(写真左から)細沼さん、川島先生、猿田さん
私の研究予定のテーマ
猿田さん「SNSによる自殺予防、自殺願望の増幅」細沼さん「趣味と自殺予防の関係」
Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです






