
研究室概要紹介
人と人とが考えや気持ちを交わして、新しい人間関係やアイデアを築いていく活動を観察します。そして、映像やコンピュータなどの情報技術を活用し、さらに面白く効果的なコミュニケーションの実現に取り組んでいます。テーマは身の回りから発見した課題を皆で議論しながら育てています。
プログラミングや電子工作で道具を作る側面と、道具を用いた結果として起こるコミュニケーションの変化を観察する側面の両方から課題に取り組み、実現力と観察眼の両方を磨きます。
小林研究室ではこんなことを学んでいます!
3年次に、自らの生活を振り返ってコミュニケーションの場面を書き出し、そこで生じる問題の原因と解決手法を考えるところから研究が始まります。日常生活で感じる問題を解決するために、情報技術をどのように活用すればよいか、自身で考える力を身に付けます。
具体的には、新しい道具のアイデアを形にするために、通信や電子工作を含む情報技術を学びます。また、人の行動を観察し、評価するために心理学や認知科学についても学びます。
大学院進学を決めた理由
コミュニケーションについて学ぶうちに、普段のコミュニケーションが複雑で面白いものであることに興味を持ちました。研究を通じて人についてより深く理解し、コミュニケーションの新しい形を開拓したいと思い、進学を決めました。
研究室の雰囲気
穏やかな雰囲気の研究室です。コミュニケーションが研究室のテーマなので人と話すことが好きな人が多いです。逆に話すのは苦手だと言う人もいますが、共通しているのは、コミュニケーションの難しさや面白さに興味を持っている点です。毎週行われるゼミには研究室の学生全員が参加し、おのおのの研究を報告し議論します。そのため、学年問わず意見を交わすことができる雰囲気があります。
先生の紹介
小林稔先生
穏やかで温かい先生です。研究室にいると積極的に声をかけてくださり、研究や進路の相談に乗ってくださいます。日常的な会話を交わすことも多く、学生と近い距離で親身になってくださる先生です。
私はこんな理由で研究室を選びました!
情報技術を日常生活で活用することに興味がありました。人と人とのコミュニケーションを支援する道具作りに取り組んでいる小林研究室では、コンピュータに3Dプリンタや電子工作も組み合わせてアイデアを形にしています。話しやすい研究室の雰囲気に加えて、コミュニケーションをはじめ自分自身が日常で感じる不便さを、情報技術を活用したものづくりで解消する点が面白そうだと思い、小林研究室を選びました。
小林研究室あれこれ
男女比・人数
男性13人:女性6人=19人
研究室の秘密道具・グッズ
「Beam」というテレプレゼンスロボット(映像と音声を組み合わせた遠隔コミュニケーションツール)が研究室の中央に設置されています。リモートからログインして室内を動き回って会話ができます。先生と「Beam」を介して、研究相談や雑談をすることもあります。
私の研究テーマ
「自身の動きの拡張により、遠隔者の動きの理解を容易にする手法の研究」
センサ情報を活用し、遠隔地の会議参加者の状態を把握可能にする方法の実現に取り組んでいます。自身の状態がどのように表示されるかをフィードバックすることで、相手の状態を直感的に理解できるインタフェースを実現できると考え、検証を行っています。
※記事中に掲載した写真は撮影時のみマスクを外すなどの配慮をしております
MEIJI NOWに出演いただける明大生の皆さんを募集しています。大学受験や留学の体験記、ゼミ・サークルの活動をMEIJI NOWで紹介してみませんか?
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです







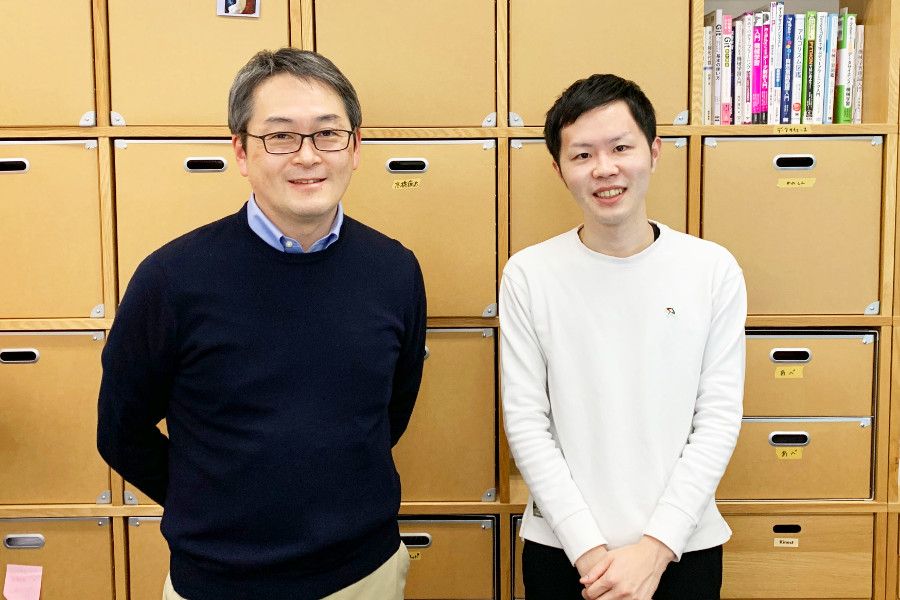
 募集案内を見る
募集案内を見る

