
 田中ゼミの集合写真
田中ゼミの集合写真ゼミ概要紹介
AI技術の導入も視野に入れつつ、ICT(※)とプラットフォームがどのように社会を変化させているのかを、主にメディア産業やコンテンツ産業を対象として、日本と諸外国の比較の視点からアプローチし、「公益に資するICTの活用とは何か」「ICT産業にかかる政策のあり方を考えること」をテーマとしています。一次資料に基づく制度比較のリサーチ手法や、データ分析手法の習得を目指しています。
※ICT:Information and Communications Technologyの略で情報通信技術のこと。
田中ゼミではこんなことを学んでいます!
3年次には、情報通信白書などから政策動向や市場動向や、先端的な動向にかかる書籍の輪読(2020年には『X-Teck 2020』)、社会科学分野のリサーチ方法の基礎を学びます。また、対外的に発表する機会もあり、情報通信学会の次世代ネット政策研究会という合同ゼミでの発表や、英国のボーンマス大学の経営系学部の学生さん向けに英語での発表やディスカッションも行いました。
具体的には、学生の関心に応じてテーマを設定し、オーディエンスの変化の分析や、DX(デジタルトランスフォーメーション)(※)にかかる企業の取り組みをリサーチして、結果を発表しています。中野区の情報化のリサーチでは、区役所の情報化のご担当者にもインタビューを実施しました。2021年度の清里ゼミ合宿では、卒業論文発表会も行いました。なお、卒業論文は、学生論集にも掲載されています。
※DX(デジタルトランスフォーメーション):進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること
アピールポイント
ICTについて知見を深めることは、現代社会において必ず役に立つことです。田中ゼミの特徴は、ICTに対する感度を、本人の意思次第でいくらでも研ぎ澄ますことができることです。ICTはどの産業とも接点があるため、研究テーマの設定において、学生の裁量が比較的大きいです。
また、先生の研究テーマがコンテンツ系もカバーしていることから、インフラ・レイヤーから上位レイヤーをカバーして、学生本意に指導・授業を展開してくださいます。また、卒業論文の執筆が必須となっていることもあり、少数精鋭で学年関係なく仲が良いため、充実したゼミライフを送ることができます。
ゼミの雰囲気
ゼミ内容を聞くだけでは、堅苦しい雰囲気を連想するかもしれませんが、基本的には和気あいあいとしており、自由闊達な雰囲気でゼミに臨むことができます。ただ、学生の色がそのまま反映されていると感じることもあり、上記の雰囲気は我々3期生の性格によるものかもしれません。ゼミ生は多かれ少なかれICT分野に関心があるため、ディスカッションや意見交換もしやすいです。そのため「雰囲気が合わない」ということがあまりなく、学生自身で雰囲気作りをすることができるのは大きな魅力です。
また、ICTやコンテンツに関する展示会や見学に行くこともあるので、理解が深まっています。

3・4年合同で日本科学未来館の『きみとロボット展』を見学
先生の紹介
田中絵麻先生
先生は、「ICT政策」や「市場のリサーチ」に長らく携わってきたことから、世界のICT動向に詳しいです。また、ICT分野、コンテンツ分野、メディアリテラシーの授業を担当されており、幅広く研究をされています。
私はこんな理由でゼミを選びました!
荒田さん:1・2年次で受講した講義を通し、ICTとそれにまつわる知識の必要性を痛感したため、本ゼミで知見を深めようと思ったからです。また、情報収集・レポート作成など、将来的にも有用な能力も高めることができると感じたからです。
土屋さん:これからの時代の中心になるICT分野を学ぶことで、時代の流れを乗りこなせると考えました。また、コンテンツ産業という自分の興味と重なる分野を交えることで、ICTが学びやすくなると思い、田中ゼミを選びました。
田中ゼミあれこれ
人数
10人
OB・OGの主な進路先
IT企業、食品会社、ゲーム会社、小売り・不動産、航空会社 など
私の研究テーマ
荒田さん「未来社会論に対する批判的考察(仮)」
土屋さん「スポーツにおいてのAI審判の可否(仮)」
※記事中に掲載した写真は撮影時のみマスクを外すなどの配慮をしております
MEIJI NOWに出演いただける明大生の皆さんを募集しています。大学受験や留学の体験記、ゼミ・サークルの活動をMEIJI NOWで紹介してみませんか?
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです








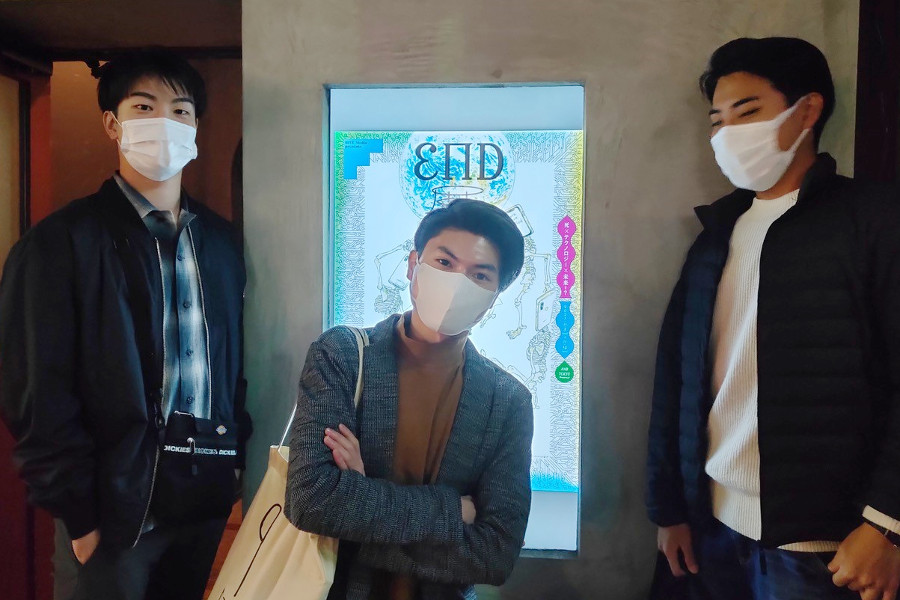

 募集案内を見る
募集案内を見る

