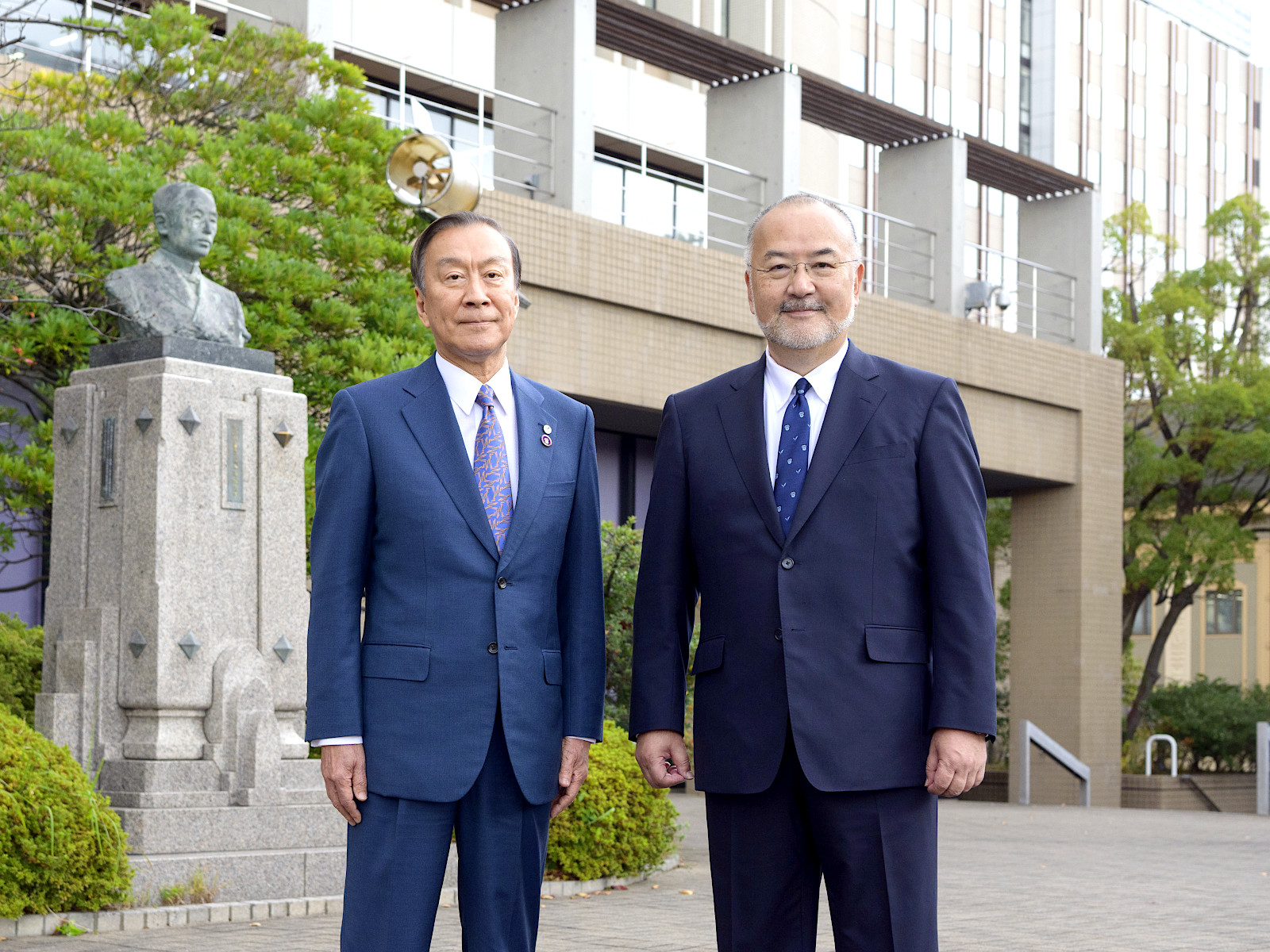シンポジウムの様子。左から小林秀行准教授、根橋玲子教授、清水晶紀准教授、島田剛教授、佐藤亜紀氏、後藤晶准教授
シンポジウムの様子。左から小林秀行准教授、根橋玲子教授、清水晶紀准教授、島田剛教授、佐藤亜紀氏、後藤晶准教授情報コミュニケーション学部は10月13日、駿河台キャンパス・リバティホールで学部創設20周年記念式典・シンポジウムを開催した。
情報コミュニケーション学部は、2004年に社会科学に立脚した新たな学問として情報コミュニケーション学を掲げ創設された。以来、多彩な分野の研究者が集う教育・研究の現場から、社会の諸現象を学際的に研究し、幅広い分野へ卒業生を輩出している。
式典の冒頭、阿部力也学部長が「情報社会のまだ見ぬ進化と共に、学問領域をつなぐ架け橋としてさらなる発展を目指す」とあいさつした。続いて、柳谷理事長から「情報コミュニケーション学部は学際性と多様性を体現する学部。今後も大いに輝き続けてほしい」、上野学長から「創設当初から高度情報社会の本格的な到来を予測し、人間と社会の在り方を学際的に究明してきた。こうした先進的な理念の下、これからも新たな価値を創造し提示してゆくと確信している」と祝辞があった。
その後、20周年記念事業の実行委員長である石川幹人教授から、記念事業の実施報告と今後の実施予定が報告された。
実施報告
| 実施日 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 5月30日 | 女性法曹界を拓いた人々-明治大学専門部女子部の足跡 | 情報コミュニケーション学部ジェンダーセンターが制作した同映像の上映会と吉田恵子元教授・細野はるみ名誉教授のトークイベント |
| 6月17日 | 師、四代目市川左團次のこと~芸能の継承をめぐって~ | 日置貴之准教授が企画し、歌舞伎俳優・市川蔦之助氏が故・市川左團次氏について語った公開セミナー |
| 6月27日 | 「違和感」から始まるジェンダー表現-アートディレクター、メディア制作、身体パフォーマンスをとおして | 大島岳助教が企画しジェンダーセンターのイベントとして実施したトークイベント |
| 7月30日 | 性別を超えて~「虎に翼」から女性活躍を考える~ | 牛尾奈緒美ゼミ主催・ジェンダーセンター共催、国際日本学部・藤本由香里ゼミらと行ったゼミ横断座談会 |
今後の実施予定
| 実施日 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 10月26日 | 研究交流祭 | 1・3・4年のゼミ対抗研究発表会。今年度は20周年を記念して50チームが参加 |
| 10月28日 | 企業トップの考えるダイバーシティ・マネジメント | ジェンダーセンター主催イベントとして、片倉正美氏(EY新日本有限責任監査法人 理事長)、小泉文明氏(株式会社メルカリ 取締役President、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長)をお招きするトークイベント |
| 11月18日 | 癒しフェス in 明大前 | 清水晶紀ゼミの企画で、明大前商店街と連携し地域活性化を目指す |
| 11月22・29日 | コピーライターが考えるブランディングとコトバの関係 | 内藤まりこ専任講師の企画で、外部のコピーライターをお招きし、ブランディングとは何かを学ぶワークショップ |
| 12月7日 | AI時代において音声はどのように保護されるべきか | 今村哲也教授の企画で、著作権に関する専門家、俳優、音楽家、声優など多彩なディスカッサントを招き、AI生成ビジネスの問題や現行法制度の課題を議論し、音声を保護するための新たな法制度の構築を目指すシンポジウム |
シンポジウムでは、学際的な研究テーマとして「災害と格差」を掲げ、東日本大震災の物心両面の影響などについて、小林秀行准教授(災害社会学)、根橋玲子教授(コミュニケーション学)、清水晶紀准教授(環境法学)、島田剛教授(国際経済学)、佐藤亜紀氏(卒業生・福島第一原発が立地する大熊町在住)、後藤晶准教授(行動経済学)による研究報告と総合討論が行われた。
 佐藤亜紀氏
佐藤亜紀氏佐藤氏は福島県大熊町で復興支援員として活動し、双葉郡や浜通りの「地域のコーディネーター」を担うHITOkumalabを設立するなど復興支援活動に従事している。本学短期大学(2006年閉学)卒業生である佐藤氏の現場からの報告と、各分野の研究者による学際的な討論がなされた。
終わりに、阿部学部長から「学部の特色である学際的な問いかけこそが現代社会の諸問題の突破口の一つとなる。20年、50年、100年先も社会科学を基軸としつつ、歩みを続けていく」とあいさつがあり盛況のうちに閉会となった。
 教員、在学生など約100人が参加した
教員、在学生など約100人が参加した