
明大生が、所属するゼミ・研究室を紹介する「ようこそ研究室へ」。今回は政治経済学部の森田さんが、川嶋周一ゼミナールを紹介してくれます!

ゼミ概要紹介
川嶋ゼミでは、「国際関係史」について2年間かけて学んでいます。「国家」だけでなく、国境を超えて活動する「国際機関」「多国籍企業」「NGO法人」「個人」など、国際関係に影響を与えるさまざまな主体の分析・考察を通じて、昨今の政治情勢・戦争・外交問題に至るまで、幅広い事象をターゲットとしています。国際関係史ゼミの概要を簡単に述べると、「どうしてこの世界はこうなったのか」「これからこの世界はどうなるのだろう」ということについて考え続ける場所です。
世の中の事象に対して常に学び続け、これらに対して常に考える姿勢がとても重要視されているので、先生とゼミ生が、共に学び考え続けていく、そんな「生きた」学びができるゼミです。
川嶋ゼミではこんなことを学んでいます!
川嶋ゼミでは、以下の流れでゼミを進めていきます。
- 3年次:国際関係史とは何か、学問的なものの見方を学ぶ
- 4年次:学んだ内容を自身の研究内容に即して応用する
主に、外書講読(『FOREIGN AFFAIRS(※1)』の英語記事の要約・討論)と文献講読(『歴史とは何か(※2)』をレジュメにまとめて発表・討論)の二軸で進めます。最近では、留学生のゼミ生も一緒に学んでいるので、英語でディスカッションを行う機会も増えています。
※1『FOREIGN AFFAIRS』:アメリカの外交問題評議会が発行する、国際政治を専門に扱った雑誌
※2『歴史とは何か』:歴史学の入門書。著者は、E.H.カー
 外書購読でディスカッションする様子
外書購読でディスカッションする様子アピールポイント
「将来は、グローバルに働きたい」と考えている人にとって、国際問題を多角的な切り口で学ぶことができる川嶋ゼミは、とてもお勧めです。専門的知識が身に付くだけではなく、ディスカッションも活発なので柔軟な思考も身に付きます。扱う内容が難しく、毎回の課題や卒業論文に求められるレベルが高いので一見大変そうに思えますが、それらを乗り越えた上で身に付いた実力は一生ものです。また、「国際関係史」という切り口がとても広いので、自分のやりたいことが見つかりやすいことも魅力の一つです。
 横須賀米軍基地を見学した時の一枚。横須賀は軍事的な施設が数多く存在し、その文化や背景には国際的な世情も絡んでくるため、非常に実践的な学びの機会になりました
横須賀米軍基地を見学した時の一枚。横須賀は軍事的な施設が数多く存在し、その文化や背景には国際的な世情も絡んでくるため、非常に実践的な学びの機会になりましたゼミの雰囲気
みんな楽しく和気あいあいとした雰囲気ですが、ディスカッション時になると活発な意見交換を行うため、めりはりの付いた人が多いです。また、留学など多様な経験をしているゼミ生もいるので、さまざまな知見から日々学びや刺激を得ることもできる、とても良いゼミです。
先生の紹介
川嶋周一先生
とても穏やかで優しく、頼りがいのある先生です。ゼミ生の些細な疑問に対しても、常に丁寧なレスポンスをいただけるので、それが励みにもなっています。いつでも落ち着いてゼミ生をほほ笑ましく見守っている、まるでお父さんのような存在です。
私はこんな理由でゼミを選びました!
「社会人になる前に、学問として国際的な社会の枠組みや規範、ニュースの内容をより深く学びたい」と思い、選びました。自分の知識が乏しく、報道を見ても「なぜ起こったのか?」を理解できていないことに危機感を覚えていたので、現在ゼミで学んでいる内容は、まさにその問いに合致していました。
以前よりも報道の背景や歴史的事象まで考えられるようになったので、「このゼミを選んで良かった」と心から思います。また、当時のゼミの先輩方が、生き生きと活動していた姿を見て、憧れたのも理由の一つです。
川嶋ゼミあれこれ
人数
21人(3年次:9人、4年次:12人)
OB・OGの主な進路
コンサルティング、メーカー、金融、IT関係、大学院進学など、幅広く多岐にわたります。
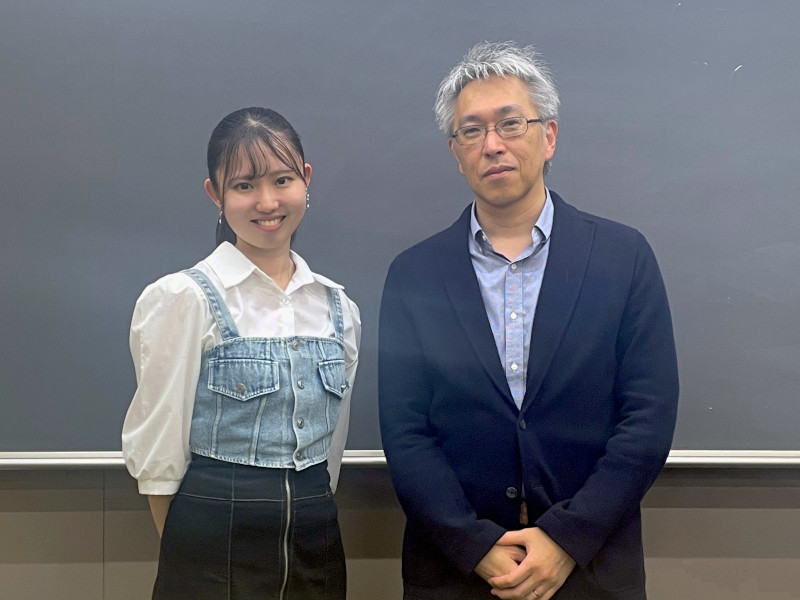 紹介者(写真左)と川嶋先生
紹介者(写真左)と川嶋先生
私の研究テーマ
「ウクライナ戦争をはじめとした戦闘における女性戦争捕虜の処遇から考察する、国際機関・国家民間レベルにおける法的保護の存在と相互作用、および課題」
Meiji NOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeiji NOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。
※ページの内容や掲載者のプロフィールなどは、記事公開当時のものです






