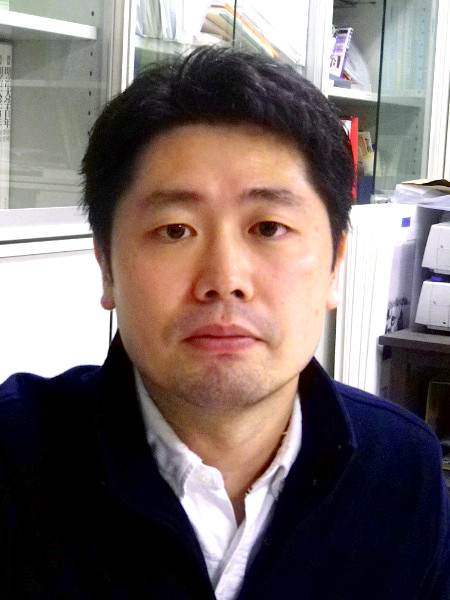
PROFILE:
1972年生まれ。国際基督教大学教養学部卒業、グラスゴー大学大学院哲学科修士課程修了、京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は西洋哲学史。2011年より明治大学農学部専任講師、2022年より同准教授。共著に、牧野英二編『新・カント読本』(法政大学出版局)、伊藤邦武他編『世界哲学史6』(筑摩書房)など。
学問を通じた知的自立
高校までの学習と大学での学習の違いとはどのようなものでしょうか。より高度な専門教育と、多様な領域にまたがる教養教育が大学教育の両輪であり、そうした専門性と多様性が大学教育の特徴であることは確かです。が、それは入口の理解に過ぎません。大学教育の出口、つまり皆さんが大学での学習を通じて目指すべき目標は、「知的な自立」です。これは専門教育にも教養教育にも言えることですので、それぞれについて考えてみます。
学問の現場に臨む
まず、大学の専門教育における学習の本質は、「知の生産現場に臨む」という点にあります。高校では、教科書に書かれていることを既存の「知識」や「事実」として受け入れることがもっぱら求められます。しかしなぜ、私たちはそれらを「正しい」ものとして受け入れているのでしょうか。
大学ではより高度で先端的な研究成果を学ぶことになりますが、学習内容がそのように先端的であるほど、「なぜそれが正しいと言えるのか?」という問いが求められます。というのは、そこで学ばれる事柄は確立された「知識」ではなく、現在進行中の研究から生み出された「暫定的な結論」だからです。そうした結論に至るための学問的な探求方法や思考法を学び、結論の「正しさ」について自分自身で考察できるということ、そのような「知的自立」が、学問の現場で学ぶ大学生としての学習目標になります。
学問を通して世界を見る
同じことは、教養教育についても言えます。教養教育の目標は、ただ単に世界について多様な知識を得るということではなく、学問の目を通して世界を見るということであり、またそのことによって、自立的な思考を習慣化させるということです。
学問とは、長年の批判的吟味を通じて得られた方法による共同的探究です。それは、「知りたい」という人間の本性的欲求を、自己批判と相互検証に根差した学問的精神へと昇華させ、独り善がりや思い込みではない「客観的な知」を目指す営みです。物理学、化学、生命科学などの自然科学は、そうした学問的探究の典型です。また政治学や経済学を含む社会科学、文学や歴史学などの人文学も、それぞれに共有された方法を通じて人間の社会活動や精神活動を捉え、独断を排した客観的・普遍的な知を求めます。
そうした学問の目を通して万物を見るという学習は、信じてよい情報と信じるべきではない情報を区別する見識を養い、さらに、そうした批判的姿勢を「生き方」として習慣化させることになります。教養教育が目指すのは、無限の情報世界の中で溺れない、自立的な精神です。それはまた、「個を強くする」という明治大学の共通理念に直結する目標でもあるのです。
 農学部めいじろう
農学部めいじろうMeijiNOWでは、Xアカウント(@meiji_now)で日々の更新情報をお知らせしています。Xをご利用の方は、以下のボタンからMeijiNOW公式アカウントをフォローして、情報収集にご活用ください。






